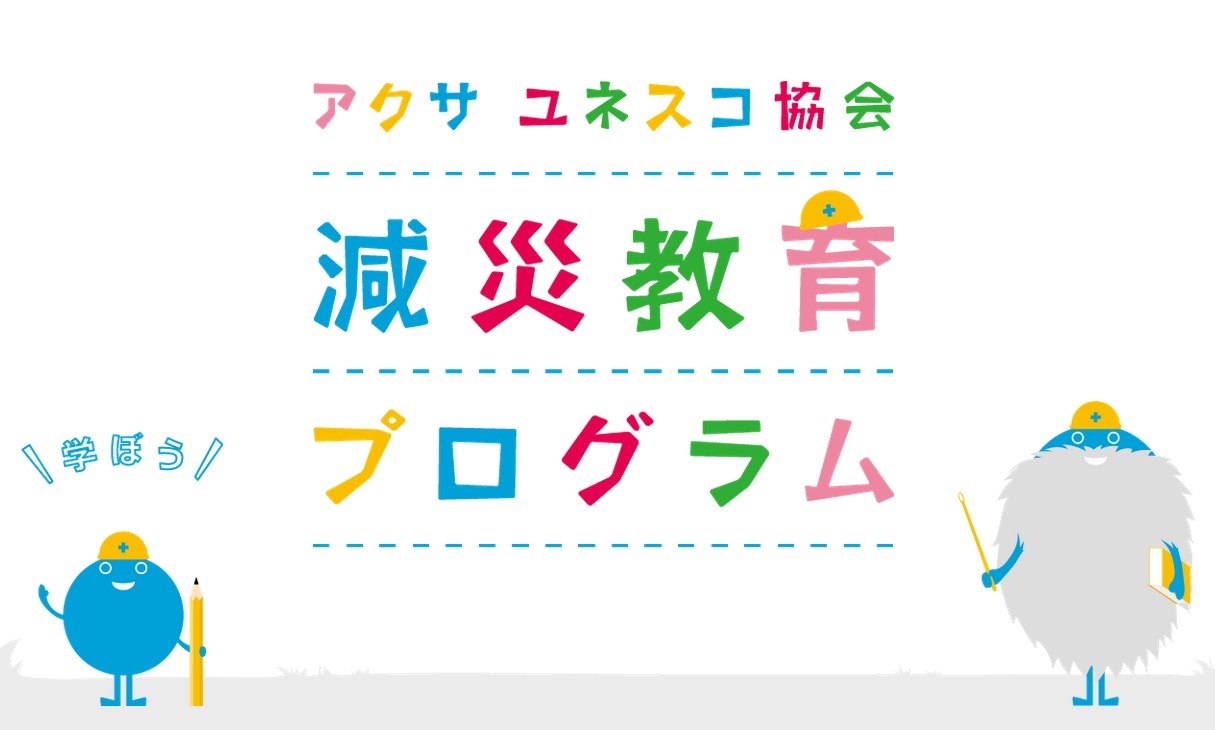
地域とはぐくむ防災意識
江戸川区立清新第二中学校
活動に参加した児童生徒数/全学年 228人
活動に携わった教員数/19人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/保護者・地域住民・その他(区職員・消防・自衛隊) 約200人
実践期間2024年10月1日~2025年3月15日
活動のねらい
2024年1月、能登半島沖地震を受け、今年度から、本校でも防災教育を学校経営方針に重要項目として位置付けた。本校は高く盛られた埋め立て地に建設されており、ハザードマップでも危険性は少なく表示されているため、生徒だけではなく、地域の大人からも危機感はあまり感じられない。そこで、生徒や保護者、地域が災害に対して正しく怖がり、当事者意識をもつことから始める必要があり、地域が一体となった活動により意識づけを行うことを第一のねらいとした。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
1学年:防災マップづくり(11月~1月)
地域の危険個所やAED設置場所、避難所までの困難な場所(車いす使用)を調べる → 実際の地域調べ(地域の方同伴) → マップづくり・発表
2学年:災害の知識を得る(10月~12月)【東京防災・タイムラインを教材として】
起こりうる災害を教材や映像から学習し、その時の状況を想像しながら避難方法やその後の行動を考える。
(探究学習)自分の避難方法は1枚のシートに、覚えやすいようにまとめる。
3学年:避難所運営(10月~2月)
避難所での必要な行動や困難なことを、以前の被災状況を調べることで把握。(探究学習:現在進行中)
避難所で自分たちができることをまとめる → 予算からダンボールベッドを購入 → 備蓄
学校:総合防災訓練(2月15日)
消防、自衛隊、役所、地域、(警察機動隊)の協力のもと、本校生徒・地域の小学6年生・保護者・地域による参加型の防災訓練を実施(別紙要綱参照)
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
昨年度までの現状は、教科の内容に紐づける形で、教科の授業中のみで防災学習を行っていた。今年度、経営方針の重要項目として位置付けたことで、総合の年間計画には位置付けたが、どのような授業を行うか困惑することもあった。9月の研修後、学校で研修を行い、内容を確定させた。物品の購入は生徒の意見を受けて決定した。実践してみて、今年度は計画段階でしっかりとした時間が確保できないことはわかっており、活動も単発的なものとなってしまったと感じている。来年度は、始めから計画的に学習できるように、教科横断型の計画を作成する。また、探求学習を各学年で取り入れ、生徒自身が当事者意識を高められるような、また、各学年が連携し、継続的な計画としていきたい。
助成金は生徒の意見「避難所での生活を見て、快適な睡眠をとれていないと感じた。改善したい」を聞いて、生徒からの要望でダンボールベッドを購入した。生徒自身でダンボールを持ち寄っての作成も考えたが、その後の備蓄として、いざというときに活用できるものとして、今回は購入することとした。生徒はそのダンボールベッドの組み立てから、さらに思考を深め、避難所での行動や快適さを求めるようになり、意識の向上につながった。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
実際は今年度の中旬から活動を開始し、単発的な計画となってしまったが、その中でも生徒はしっかりと考え、意見を共有し、そこから自分の考えをある程度確立させることができた。重要項目として位置付けられた初年度としては改善の余地しかなく、教科横断的で3年間を見通した計画を立てる必要がある。また、様々なところで地域と連携した活動を取り入れ、「地域とともにはぐくむ減災意識」を高めていきたい。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
少ない時間ではあるが、調べ学習や探究学習を取り入れ、自分の地域や災害について考えることができ、少なからず、「災害は恐ろしい」「起きることを止められない」「災害後の準備の大切さ」をそれぞれの思いで感じ取ることができた。
活動中に、田舎に住む祖父母のことが気になり、その地域まで調べる生徒もいた。防災から減災という意識をもつようにもなった。また、地域の方と交流したことで、違う意味でも連携をつくることができた。実際に起きてしまったときに、何かしらの活動を行えるようになるまで、すばやい避難や救護活動、避難所運営ができるようになるまで、そのシミュレーションができるようになるまで、計画的かつ継続的な学習計画を確立させていかなければならない。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
災害の少ない地域で暮らし人にとって、被災地に暮らす人の意識をもつことはできない。どのように近づけていけるかを模索しながら、当事者意識を育てる取り組みを考えてきた。1年生は地域の方と触れ合いながら、今まで知らなかった地域での防災対策や備品を知って、お互いの意識を高められたと感じている。また、成果としてはこれからであるが、2月の総合防災訓練では、計画段階から地域の方に評価されている。教員側としては、知識等は身につけているが、実際それが生かせるのかと考えた場合、それだけの自信がない教員も少なくない。今回、生徒に様々なことを考えさせるとともに教員も学ぶことができた。学校だけでは限界があり、限定的な取り組みになってしまうが、地域と一体となって減災、防災教育に取り組むことが、お互いの意識を高めるには一番の活動だと考え、今後も立案、遂行していきたい
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
各学年の実践を見てきて、今年度は単発的な計画となってしまったが、その中でも、地域の協力を得たり、予算があると減災・防災に対する意識はそれなりに向上することが確認できた。しかしながら、やはり、計画的・継続的・連続性が必要だと感じる。また、学年の枠を超えた学習、小学校との連携、地域との共存など、様々な要素を取り入れていかなければならない学習であると強く思わされた。当然のごとく見直しは必要不可欠ではあるが、まずは年間指導計画であるが、各学年に内容を任せるのではなく、発達段階を考慮し、学校全体としての教科横断的な学習として立案する。生徒が自主的に行えるような探求学習を中心とする。また、保護者や地域との連携強化を図り、全員で地域の減災に努める意識をもてるプログラムも考えていきたい。
1学年:防災マップづくり(11月~1月)
地域の危険個所やAED設置場所、避難所までの困難な場所(車いす使用)を調べる → 実際の地域調べ(地域の方同伴) → マップづくり・発表
2学年:災害の知識を得る(10月~12月)【東京防災・タイムラインを教材として】
起こりうる災害を教材や映像から学習し、その時の状況を想像しながら避難方法やその後の行動を考える。
(探究学習)自分の避難方法は1枚のシートに、覚えやすいようにまとめる。
3学年:避難所運営(10月~2月)
避難所での必要な行動や困難なことを、以前の被災状況を調べることで把握。(探究学習:現在進行中)
避難所で自分たちができることをまとめる → 予算からダンボールベッドを購入 → 備蓄
学校:総合防災訓練(2月15日)
消防、自衛隊、役所、地域、(警察機動隊)の協力のもと、本校生徒・地域の小学6年生・保護者・地域による参加型の防災訓練を実施(別紙要綱参照)
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
昨年度までの現状は、教科の内容に紐づける形で、教科の授業中のみで防災学習を行っていた。今年度、経営方針の重要項目として位置付けたことで、総合の年間計画には位置付けたが、どのような授業を行うか困惑することもあった。9月の研修後、学校で研修を行い、内容を確定させた。物品の購入は生徒の意見を受けて決定した。実践してみて、今年度は計画段階でしっかりとした時間が確保できないことはわかっており、活動も単発的なものとなってしまったと感じている。来年度は、始めから計画的に学習できるように、教科横断型の計画を作成する。また、探求学習を各学年で取り入れ、生徒自身が当事者意識を高められるような、また、各学年が連携し、継続的な計画としていきたい。
助成金は生徒の意見「避難所での生活を見て、快適な睡眠をとれていないと感じた。改善したい」を聞いて、生徒からの要望でダンボールベッドを購入した。生徒自身でダンボールを持ち寄っての作成も考えたが、その後の備蓄として、いざというときに活用できるものとして、今回は購入することとした。生徒はそのダンボールベッドの組み立てから、さらに思考を深め、避難所での行動や快適さを求めるようになり、意識の向上につながった。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
実際は今年度の中旬から活動を開始し、単発的な計画となってしまったが、その中でも生徒はしっかりと考え、意見を共有し、そこから自分の考えをある程度確立させることができた。重要項目として位置付けられた初年度としては改善の余地しかなく、教科横断的で3年間を見通した計画を立てる必要がある。また、様々なところで地域と連携した活動を取り入れ、「地域とともにはぐくむ減災意識」を高めていきたい。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
少ない時間ではあるが、調べ学習や探究学習を取り入れ、自分の地域や災害について考えることができ、少なからず、「災害は恐ろしい」「起きることを止められない」「災害後の準備の大切さ」をそれぞれの思いで感じ取ることができた。
活動中に、田舎に住む祖父母のことが気になり、その地域まで調べる生徒もいた。防災から減災という意識をもつようにもなった。また、地域の方と交流したことで、違う意味でも連携をつくることができた。実際に起きてしまったときに、何かしらの活動を行えるようになるまで、すばやい避難や救護活動、避難所運営ができるようになるまで、そのシミュレーションができるようになるまで、計画的かつ継続的な学習計画を確立させていかなければならない。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
災害の少ない地域で暮らし人にとって、被災地に暮らす人の意識をもつことはできない。どのように近づけていけるかを模索しながら、当事者意識を育てる取り組みを考えてきた。1年生は地域の方と触れ合いながら、今まで知らなかった地域での防災対策や備品を知って、お互いの意識を高められたと感じている。また、成果としてはこれからであるが、2月の総合防災訓練では、計画段階から地域の方に評価されている。教員側としては、知識等は身につけているが、実際それが生かせるのかと考えた場合、それだけの自信がない教員も少なくない。今回、生徒に様々なことを考えさせるとともに教員も学ぶことができた。学校だけでは限界があり、限定的な取り組みになってしまうが、地域と一体となって減災、防災教育に取り組むことが、お互いの意識を高めるには一番の活動だと考え、今後も立案、遂行していきたい
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
各学年の実践を見てきて、今年度は単発的な計画となってしまったが、その中でも、地域の協力を得たり、予算があると減災・防災に対する意識はそれなりに向上することが確認できた。しかしながら、やはり、計画的・継続的・連続性が必要だと感じる。また、学年の枠を超えた学習、小学校との連携、地域との共存など、様々な要素を取り入れていかなければならない学習であると強く思わされた。当然のごとく見直しは必要不可欠ではあるが、まずは年間指導計画であるが、各学年に内容を任せるのではなく、発達段階を考慮し、学校全体としての教科横断的な学習として立案する。生徒が自主的に行えるような探求学習を中心とする。また、保護者や地域との連携強化を図り、全員で地域の減災に努める意識をもてるプログラムも考えていきたい。
活動内容写真
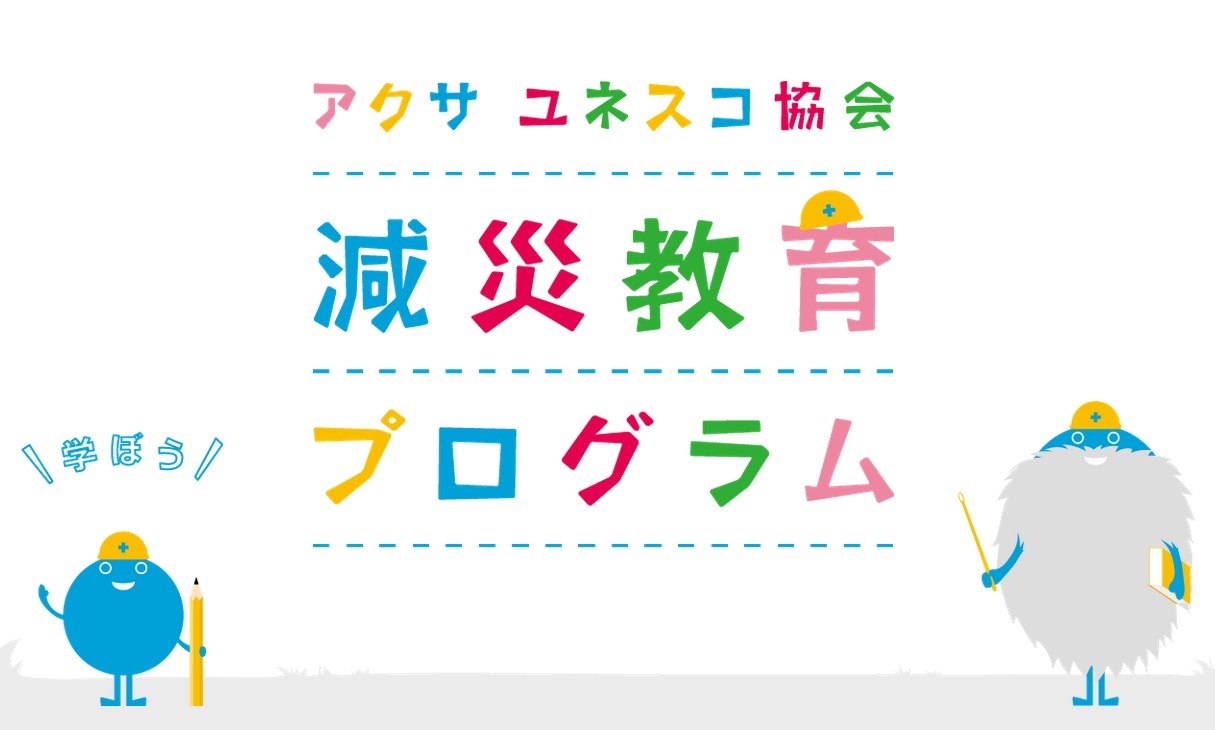
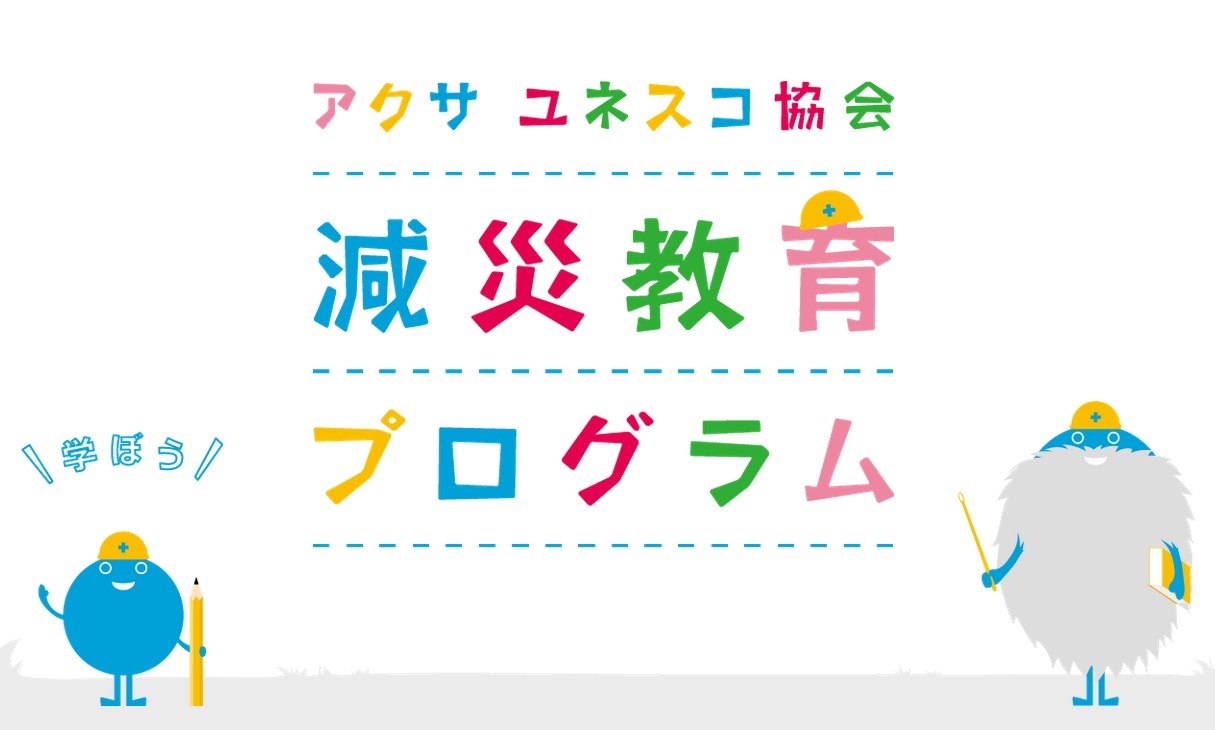
活動において工夫した点
いただいた予算を、実際に生徒が必要だと考えた物品を購入できたことである。本来なら教員側で計画に基づき購入するべきではあると思うが、こちらも予期していた物品であったこともあり、生徒の希望に沿った形での購入とした。生徒側からすると、希望通りにいったことが、この学習で意欲的になった一つの要因だと思われる。また、2月に行われる総合防災訓練では、例年消防署のみ協力いただいていたが、今年度から消防に加え、自衛隊、地域、区役所、PTAの協力を得て、地域の小学生とその保護者も参加していただく計画としている。来年度は自治体からのブースや警察機動隊の協力も得る予定である。地域一帯で取り組むことで意識の向上を図りたい。

