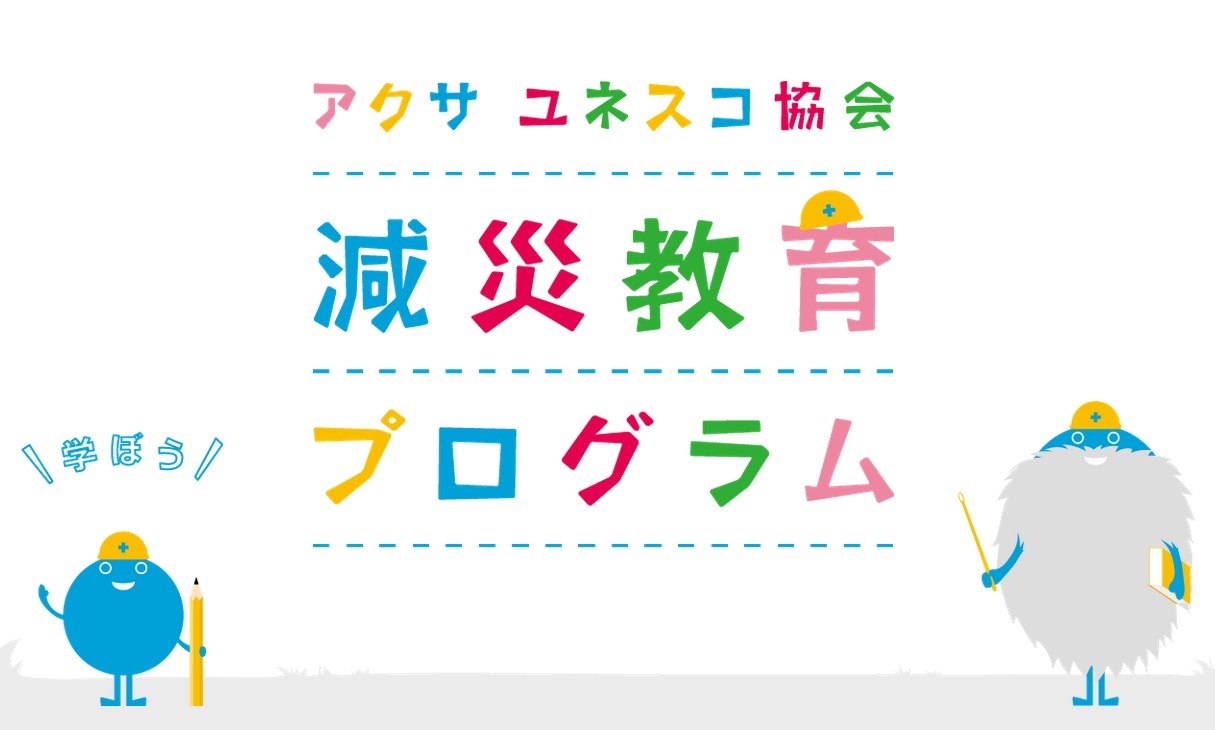
私たちにできる防災・減災~岩国地域の災害の歴史を通じて~
学校法人高水学園
高水高等学校
活動に参加した児童生徒数/2学年5人、1学年5人 計10人
活動に携わった教員数/1人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/保護者・地域住民・その他(学芸員など) 5人
実践期間2024年5月21日~2025年2月15日
活動のねらい
本校の生徒は大学を卒業後、地元岩国に戻り家業を継ぐ生徒も多い。彼らは仕事に従事する傍ら、青年会議所に所属して地域課題の解決や次世代の育成など、地域社会にポジティブな変化をもたらす様々な活動を行っている。岩国市は梅雨・台風の時期に洪水のリスクが高く、川の氾濫や大雨により住宅地や農地が浸水し、住民の生活に大きな影響を与えることがある。洪水被害は、市民に生命の危機を及ぼすだけでなく、市のインフラに大きな打撃を与え、復旧には多くの時間と資源が必要とされる。防災・減災の知識を身につけた本校の卒業生が地元に戻り、多世代の地域住民と交流・活動することで、地域住民に災害に対する意識を浸透させることができると考えた。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
5月21日:オリエンテーション
5月28日:文献検索(学校図書館)
6月3日:文献検索(学校図書館)
6月11・18日:岩国市の災害について発表
6月25日:岩国徴古館枝元学芸員の講演「歴史から学ぶ岩国地域の災害」
7月16日:日本赤十字の防災・減災活動について考察
夏休み中:岩国科学センター、防災学習館を訪問し、防災に対する知識を習得 国ユネスコ協会主催防災キャンプへ参加(1泊2日)
9月3日:山口大学佐村准教授の講演「ジオインテリジェンスとは何か?人工衛星による地球観測と知能化技術」
9月9日: 夏休み中の活動報告まとめ
9月17日:2月の発表会に向けて担当決め
9月24日:教員研修会の復伝
10月1・8日:中間発表へ向けてスライド作成
10月22日:日本赤十字社防災セミナー受講「三角巾を用いた応急処置」
10月29日~:岩国地域の災害に関する歴史から今後起こり得る災害を想定し、自分たちができることについて
プレゼンテーション・研究紀要冊子にまとめた。
2月15日:探究学習の成果を学習発表会で披露した。
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
東日本大震災の被災地を訪問し、現地の状況や被災者の声を直接聞くことは、災害のリアリティを強く感じる貴重な機会となった。被災地で見た現実は、防災計画や訓練の重要性を深く理解させてくれた。震災後の混乱や避難の過程、そして長期的な復興活動を目の当たりにすることで、災害対策の計画を具体的かつ現実的に考えることの重要性を痛感した。この体験を生徒たちに伝えることで、災害対策の具体的な行動計画を立てる際の参考とさせていただいた。
また、被災者の方々がどのようにして困難な状況を乗り越えたのか、彼らの話を聞くことで、人々がどれだけ強い意志とコミュニティの支えを持っているのかを知ることができた。この点を教育の一環として取り入れ、災害時の心のケアやコミュニティの重要性についても生徒たちに学ばせる必要性を痛感させられた。9月の研修では、単なる知識の伝達にとどまらず、実際の行動に結びつけることができる貴重な機会となった。このリアルな体験を通じて、自分自身、防災・減災に対する意識と行動力を高めることができた。また、助成金があることで費用面での心配なく、外部講師の招へいや物品の購入を行えることは大変ありがたいと感じた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
災害がいつどこで起こるか予測することは難しいが、事前に備えておくことは、命を守るために不可欠である。減災・防災教育は単なる知識の習得にとどまらず、何よりも自分自身のこととしてとらえることが大切だ。このことは、被災地を訪問した際、祖父母から実体験を聞いて育った中学生の総合的な学習の学びの成果発表を聞いた時に痛感させられた。
まず、災害が発生した際に最も重要なのは、迅速かつ的確な行動である。防災教育を通じて、避難経路や安全な場所を日頃から確認しておくこと、自宅や職場、学校での避難訓練を実施することが求められる。しかし、これらの知識や訓練は、他人ごとと捉えてしまうと実際の災害時には役立たない。自分の命を守るための行動だと意識することで、初めて有効に活用できる。また、災害時には家族や友人、地域の人々との協力が不可欠である。自分のこととして防災を考えることで、周囲の人々にも防災の重要性を伝えることができ、コミュニティ全体の防災意識も高まる。例えば、災害時に備えて家族と避難計画を立てたり、地域の防災訓練に積極的に参加することで、実際の災害時にスムーズな避難が可能となる。
防災・減災教育は、自分のこととしてとらえることで、その意義と重要性がより一層深まる。私たち一人ひとりが防災の意識を持ち、自ら行動することで、安全で安心な社会を築くことができる。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
【学び(変容)】
危機意識の向上: 災害への理解が深まり、自分自身や他者を守る意識が高まった。
リスク評価能力の向上: 日常生活でのリスクを自ら評価し、適切な対応策を考える力が養われた。
コミュニティの重要性の認識: 災害時の協力や連帯の大切さを理解し、地域社会への関心が高まった。
【資質・能力・態度】
問題解決能力: 災害が起きた際に冷静かつ迅速に対応する力が身についた。
リーダーシップとフォロワーシップ: 協力し合い、役割を分担して行動する能力が養われた。
応急処置のスキル: 怪我や緊急事態に対処するための基本的な医療知識や技術が身についた。
持続可能な生活習慣: 資源の節約や環境保護についての意識が高まり、持続可能な生活習慣が身についた。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
防災教育は、理科、地理、保健、家庭科など、多くの教科に関連する総合的な教育の一環として位置づけられる。これにより、生徒は広範な知識とスキルを統合して学ぶことができる。教員が心がけておかなければならないことは、防災教育は他の教科と統合し、総合的な学びの一部として組み込む、教科横断的な取り組みが必要な教育であるということだ。
4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
今回の防災・減災教育では、多くの体験を通じて生徒たちに多様な学びを提供したが、その一方で内容が多岐にわたったため、一部の生徒にとって消化不良となってしまったことが課題として浮き彫りになった。この経験を踏まえ、次年度の活動ではより焦点を絞り、特定のテーマに集中した取り組みを行いたいと考えている。具体的には、本校が避難所に指定されているという特性を活かし、実際の災害を想定した取り組みを行いたいと考えている。生徒たちは、ボランティアとしてどのような活動ができるかを探究し、具体的な行動計画を立てていく。生徒たちが緊急時に自らの安全を確保し、他者を支援するための実践的なスキルを深く学べるようにすることが目標である。焦点を絞った取り組みにより、生徒たちはより深い理解と確実なスキルの習得が期待される。引き続き、防災・減災教育の重要性を伝え、生徒たちがより安全で安心な生活を送るためのサポートを続けていきたい。
5月21日:オリエンテーション
5月28日:文献検索(学校図書館)
6月3日:文献検索(学校図書館)
6月11・18日:岩国市の災害について発表
6月25日:岩国徴古館枝元学芸員の講演「歴史から学ぶ岩国地域の災害」
7月16日:日本赤十字の防災・減災活動について考察
夏休み中:岩国科学センター、防災学習館を訪問し、防災に対する知識を習得 国ユネスコ協会主催防災キャンプへ参加(1泊2日)
9月3日:山口大学佐村准教授の講演「ジオインテリジェンスとは何か?人工衛星による地球観測と知能化技術」
9月9日: 夏休み中の活動報告まとめ
9月17日:2月の発表会に向けて担当決め
9月24日:教員研修会の復伝
10月1・8日:中間発表へ向けてスライド作成
10月22日:日本赤十字社防災セミナー受講「三角巾を用いた応急処置」
10月29日~:岩国地域の災害に関する歴史から今後起こり得る災害を想定し、自分たちができることについて
プレゼンテーション・研究紀要冊子にまとめた。
2月15日:探究学習の成果を学習発表会で披露した。
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
東日本大震災の被災地を訪問し、現地の状況や被災者の声を直接聞くことは、災害のリアリティを強く感じる貴重な機会となった。被災地で見た現実は、防災計画や訓練の重要性を深く理解させてくれた。震災後の混乱や避難の過程、そして長期的な復興活動を目の当たりにすることで、災害対策の計画を具体的かつ現実的に考えることの重要性を痛感した。この体験を生徒たちに伝えることで、災害対策の具体的な行動計画を立てる際の参考とさせていただいた。
また、被災者の方々がどのようにして困難な状況を乗り越えたのか、彼らの話を聞くことで、人々がどれだけ強い意志とコミュニティの支えを持っているのかを知ることができた。この点を教育の一環として取り入れ、災害時の心のケアやコミュニティの重要性についても生徒たちに学ばせる必要性を痛感させられた。9月の研修では、単なる知識の伝達にとどまらず、実際の行動に結びつけることができる貴重な機会となった。このリアルな体験を通じて、自分自身、防災・減災に対する意識と行動力を高めることができた。また、助成金があることで費用面での心配なく、外部講師の招へいや物品の購入を行えることは大変ありがたいと感じた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
災害がいつどこで起こるか予測することは難しいが、事前に備えておくことは、命を守るために不可欠である。減災・防災教育は単なる知識の習得にとどまらず、何よりも自分自身のこととしてとらえることが大切だ。このことは、被災地を訪問した際、祖父母から実体験を聞いて育った中学生の総合的な学習の学びの成果発表を聞いた時に痛感させられた。
まず、災害が発生した際に最も重要なのは、迅速かつ的確な行動である。防災教育を通じて、避難経路や安全な場所を日頃から確認しておくこと、自宅や職場、学校での避難訓練を実施することが求められる。しかし、これらの知識や訓練は、他人ごとと捉えてしまうと実際の災害時には役立たない。自分の命を守るための行動だと意識することで、初めて有効に活用できる。また、災害時には家族や友人、地域の人々との協力が不可欠である。自分のこととして防災を考えることで、周囲の人々にも防災の重要性を伝えることができ、コミュニティ全体の防災意識も高まる。例えば、災害時に備えて家族と避難計画を立てたり、地域の防災訓練に積極的に参加することで、実際の災害時にスムーズな避難が可能となる。
防災・減災教育は、自分のこととしてとらえることで、その意義と重要性がより一層深まる。私たち一人ひとりが防災の意識を持ち、自ら行動することで、安全で安心な社会を築くことができる。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
【学び(変容)】
危機意識の向上: 災害への理解が深まり、自分自身や他者を守る意識が高まった。
リスク評価能力の向上: 日常生活でのリスクを自ら評価し、適切な対応策を考える力が養われた。
コミュニティの重要性の認識: 災害時の協力や連帯の大切さを理解し、地域社会への関心が高まった。
【資質・能力・態度】
問題解決能力: 災害が起きた際に冷静かつ迅速に対応する力が身についた。
リーダーシップとフォロワーシップ: 協力し合い、役割を分担して行動する能力が養われた。
応急処置のスキル: 怪我や緊急事態に対処するための基本的な医療知識や技術が身についた。
持続可能な生活習慣: 資源の節約や環境保護についての意識が高まり、持続可能な生活習慣が身についた。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
防災教育は、理科、地理、保健、家庭科など、多くの教科に関連する総合的な教育の一環として位置づけられる。これにより、生徒は広範な知識とスキルを統合して学ぶことができる。教員が心がけておかなければならないことは、防災教育は他の教科と統合し、総合的な学びの一部として組み込む、教科横断的な取り組みが必要な教育であるということだ。
4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
今回の防災・減災教育では、多くの体験を通じて生徒たちに多様な学びを提供したが、その一方で内容が多岐にわたったため、一部の生徒にとって消化不良となってしまったことが課題として浮き彫りになった。この経験を踏まえ、次年度の活動ではより焦点を絞り、特定のテーマに集中した取り組みを行いたいと考えている。具体的には、本校が避難所に指定されているという特性を活かし、実際の災害を想定した取り組みを行いたいと考えている。生徒たちは、ボランティアとしてどのような活動ができるかを探究し、具体的な行動計画を立てていく。生徒たちが緊急時に自らの安全を確保し、他者を支援するための実践的なスキルを深く学べるようにすることが目標である。焦点を絞った取り組みにより、生徒たちはより深い理解と確実なスキルの習得が期待される。引き続き、防災・減災教育の重要性を伝え、生徒たちがより安全で安心な生活を送るためのサポートを続けていきたい。
活動内容写真
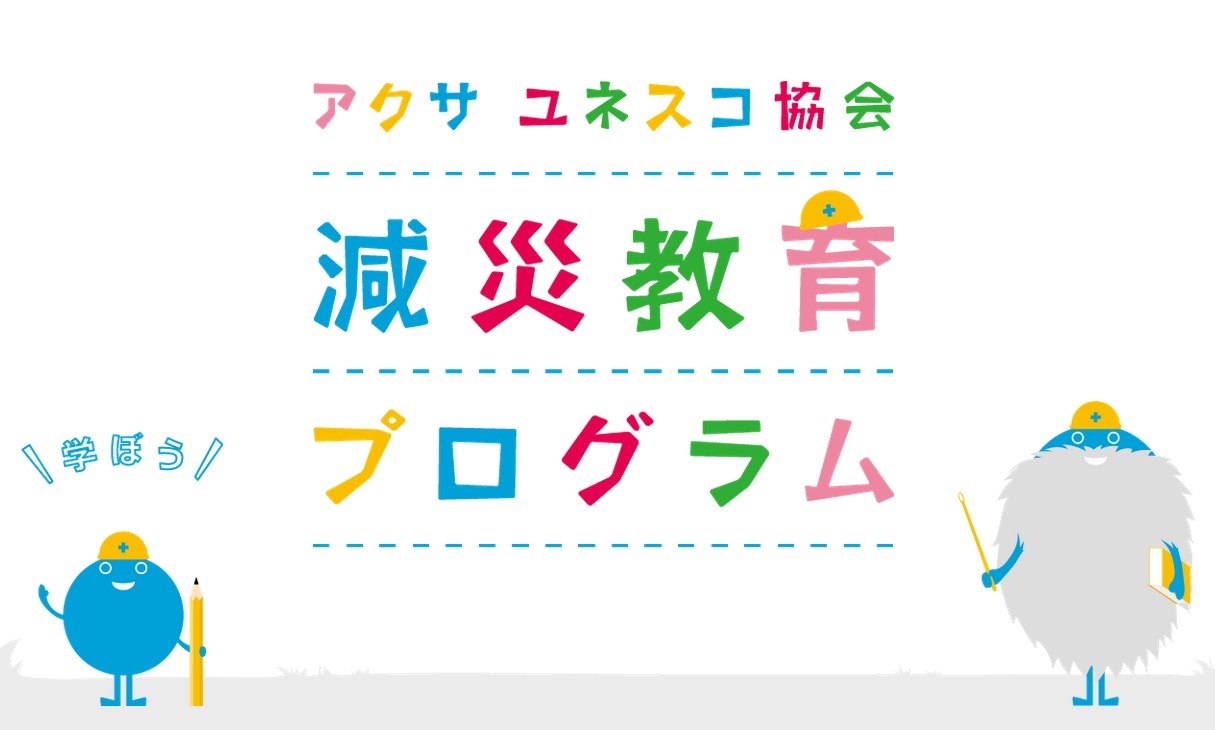
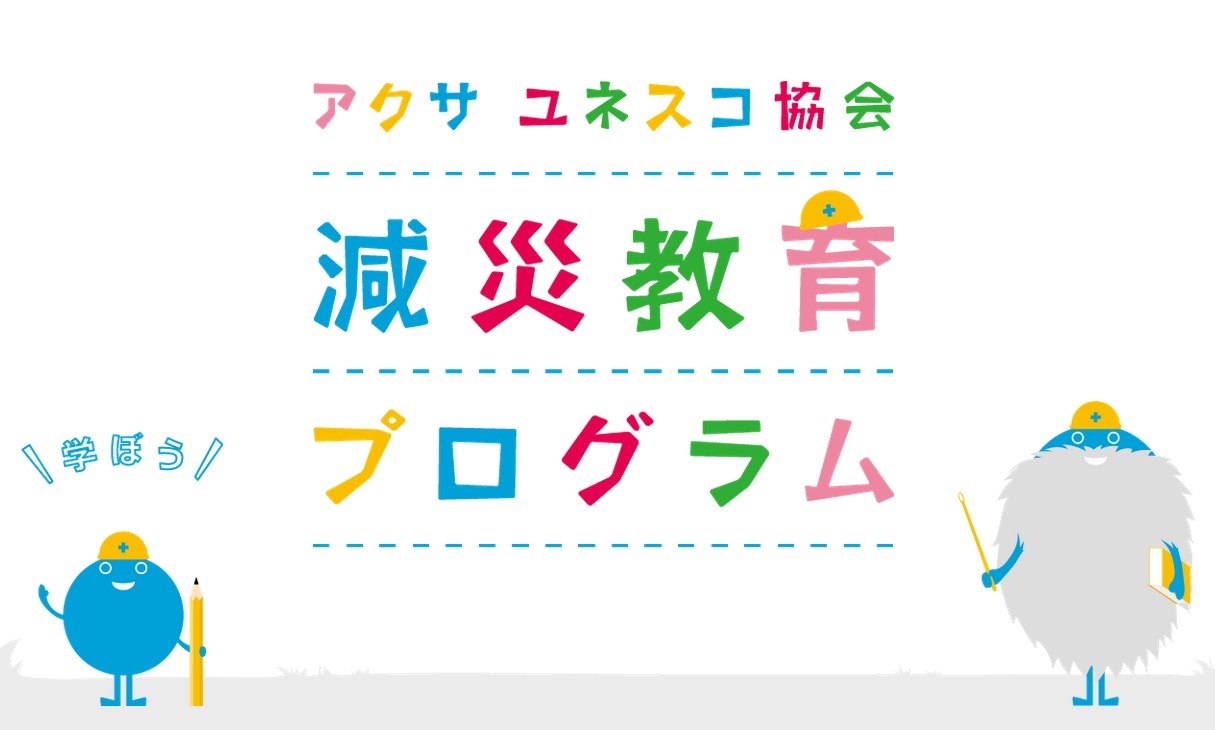
活動において工夫した点
今回の防災・減災教育では、様々な分野の専門家から直接お話を伺う機会を設けた。これにより、生徒たちは単なる理論ではなく、実際の事例や経験に基づいた知識を深めることができた。また、実際に防災学習館を訪問し、自分自身の身を守る方法を体験することで、実践的なスキルを身につけることができた。特に重視したのは、デジタルデバイスを使用した調べ学習だけに頼るのではなく、実際に体験し、他者との対話を通じて学ぶことである。これにより、生徒たちはより深い理解と実践的な対応力を養うことができた。このように、多角的なアプローチを通じて、生徒たちは防災・減災の重要性を肌で感じ、実際の災害時に役立つ知識とスキルを身につけることができた。

