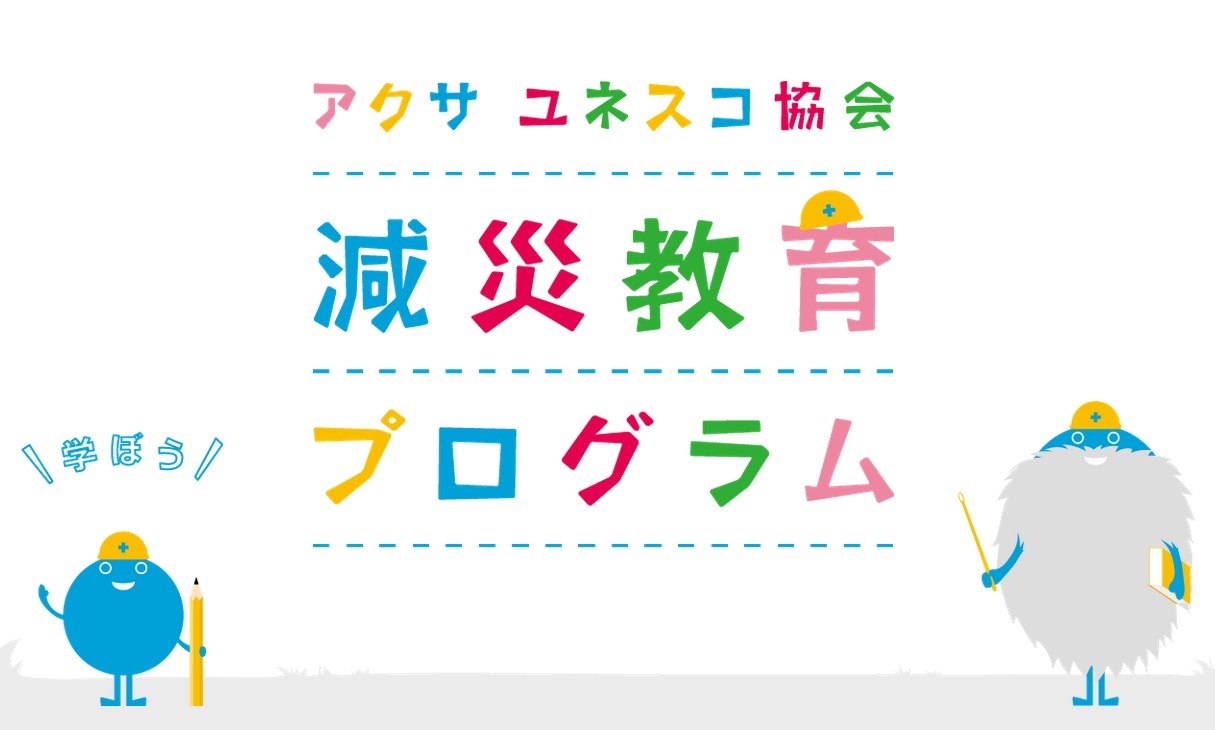
減災・防災への関心を高めるために
福島県立福島高等学校
活動に参加した児童生徒数/1学年 280人
活動に携わった教員数/15人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/地域住民・その他(大学教授、県内の企業関係者)50人
実践期間2024年5月1日~2024年12月28日
活動のねらい
東日本大震災から13年が経過したものの、直接的に被災し、津波の危険性を実感できる県内沿岸部の高校生に比べて、内陸部に位置する高校であるため生徒自身の災害に対する認識が高いとは言えない。自分が通う高校が発災時に避難所になる意味を理解できていない生徒も多く、生徒自身が授業内外で防災・減災について「自分事」として考える機会も極めて少ない。しかし、地域を牽引するリーダーの育成を掲げる高校だからこそ、福島の防災・減災や今後のエネルギーのあり方などについて考える機会を創出したいと考えた。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
①地理総合での授業1
・大地形、小地形、防災について(5~6月)
・地球温暖化などの環境問題について(7月)
②リベラルゼミによる東日本大震災伝承館、請戸小学校の訪問、浪江町のフィールドワーク(8月)
③探究活動におけるフィールドワーク(10月上旬)
→事業所、地域の抱える社会的な課題とその解決方法について学ぶ
例:日本大学工学部…再生可能エネルギーの研究について
大和川酒造…地元の木材を使ったバイオマス発電による日本酒作り
原町火力発電所…二酸化炭素の排出量を減らす取り組み
④フィールドワークを通じて学んだことをまとめてグループで発表(10月中旬)
⑤地理総合での授業2
→エネルギー問題について(11月)
⑥探究活動における高大接続講座(12月上旬)
→福島大学の教授による講座を受講
例:カーボンニュートラル、放射能について
⑦中間貯蔵施設の見学(12月下旬)
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
<9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと>
・実際に現地を見る機会を作ること。
→リベラルゼミで希望者を募り、東日本大震災伝承館に行った。
・現地の見学に加えて、震災を直接経験した人から話を聞く機会を作ること。
→リベラルゼミで浪江町のフィールドワークを行ったとき、震災当時浪江町に自宅があり、大変な思いをされた本校教員から当時の様子を話してもらったり、荒れ果ててしまった自宅を案内してもらったりした。
<助成金の活用で可能になったこと>
・助成金の活用によって、大熊町にある中間貯蔵施設の見学に加え、他校との交流をする機会を作ることができた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
9月の研修会を通じて、現地を実際にみること、実際に震災を経験した人から話を聞くこと、地域との連携などの大切さを実感した。今回はそれらを含んだ活動ができたのではないかと考える。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・地理総合の授業を通じて、地形と自然災害との関係に関する知識、ハザードマップを活用する技能などを身につけた。
・地理総合の授業やフィールドワークなどの様々な活動を経て、来年度の探究活動では「減災・防災」や「エネルギー」をテーマにしたいという生徒が出てきており、減災・防災に関する関心が高まったと思われる。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
原子力発電の事故を受けて、福島県では再生可能エネルギーのさらなる普及を目指している。ただ、知識として知っていても、具体的にどのような取り組みが行われているのかを知らなければ興味・関心は高まらないはずである。しかし、本校では1年次の探究活動の時間において、県内各地の企業や福島大学の教授から再生可能エネルギーに関する話を 聞くことができる機会が設けられており、今後のエネルギーのあるべき姿について考えることができたと思われる。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
知識をインプットするまではよかったが、その知識をアウトプットする機会をあまり持てなかったので、来年度はその部分を意識して実践していきたいと考えている。
①地理総合での授業1
・大地形、小地形、防災について(5~6月)
・地球温暖化などの環境問題について(7月)
②リベラルゼミによる東日本大震災伝承館、請戸小学校の訪問、浪江町のフィールドワーク(8月)
③探究活動におけるフィールドワーク(10月上旬)
→事業所、地域の抱える社会的な課題とその解決方法について学ぶ
例:日本大学工学部…再生可能エネルギーの研究について
大和川酒造…地元の木材を使ったバイオマス発電による日本酒作り
原町火力発電所…二酸化炭素の排出量を減らす取り組み
④フィールドワークを通じて学んだことをまとめてグループで発表(10月中旬)
⑤地理総合での授業2
→エネルギー問題について(11月)
⑥探究活動における高大接続講座(12月上旬)
→福島大学の教授による講座を受講
例:カーボンニュートラル、放射能について
⑦中間貯蔵施設の見学(12月下旬)
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
<9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと>
・実際に現地を見る機会を作ること。
→リベラルゼミで希望者を募り、東日本大震災伝承館に行った。
・現地の見学に加えて、震災を直接経験した人から話を聞く機会を作ること。
→リベラルゼミで浪江町のフィールドワークを行ったとき、震災当時浪江町に自宅があり、大変な思いをされた本校教員から当時の様子を話してもらったり、荒れ果ててしまった自宅を案内してもらったりした。
<助成金の活用で可能になったこと>
・助成金の活用によって、大熊町にある中間貯蔵施設の見学に加え、他校との交流をする機会を作ることができた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
9月の研修会を通じて、現地を実際にみること、実際に震災を経験した人から話を聞くこと、地域との連携などの大切さを実感した。今回はそれらを含んだ活動ができたのではないかと考える。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・地理総合の授業を通じて、地形と自然災害との関係に関する知識、ハザードマップを活用する技能などを身につけた。
・地理総合の授業やフィールドワークなどの様々な活動を経て、来年度の探究活動では「減災・防災」や「エネルギー」をテーマにしたいという生徒が出てきており、減災・防災に関する関心が高まったと思われる。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
原子力発電の事故を受けて、福島県では再生可能エネルギーのさらなる普及を目指している。ただ、知識として知っていても、具体的にどのような取り組みが行われているのかを知らなければ興味・関心は高まらないはずである。しかし、本校では1年次の探究活動の時間において、県内各地の企業や福島大学の教授から再生可能エネルギーに関する話を 聞くことができる機会が設けられており、今後のエネルギーのあるべき姿について考えることができたと思われる。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
知識をインプットするまではよかったが、その知識をアウトプットする機会をあまり持てなかったので、来年度はその部分を意識して実践していきたいと考えている。
活動内容写真
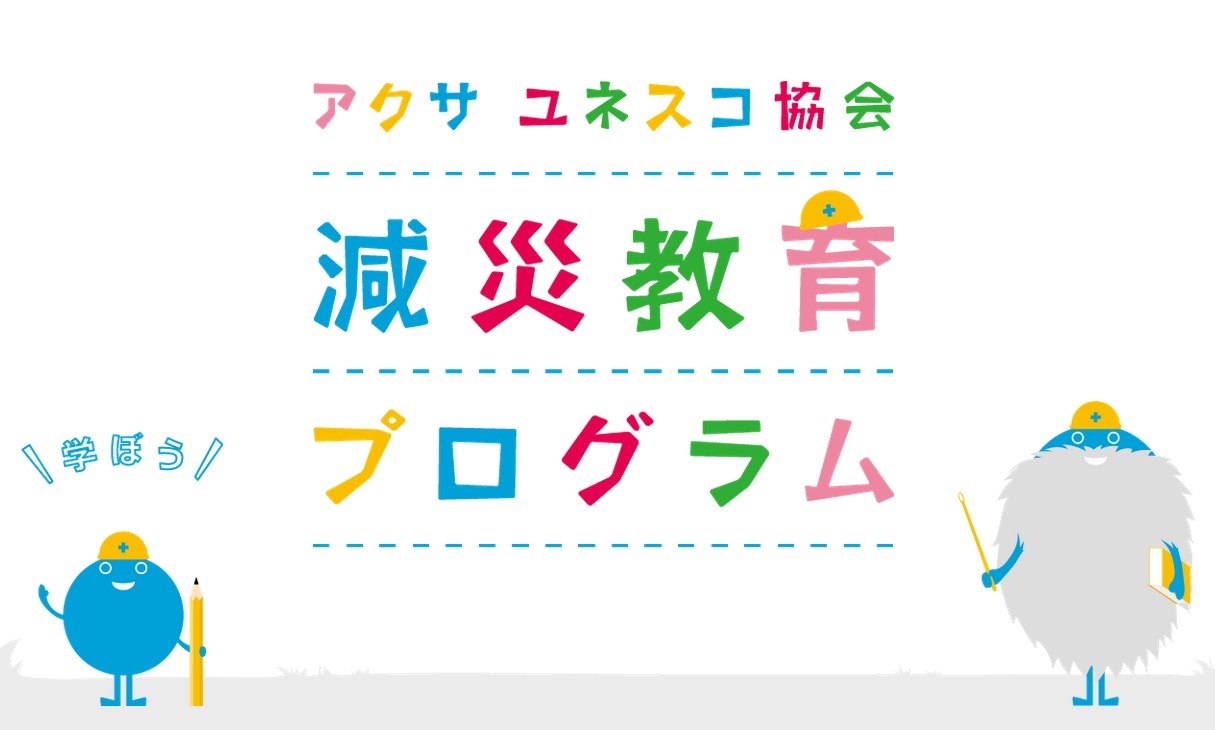
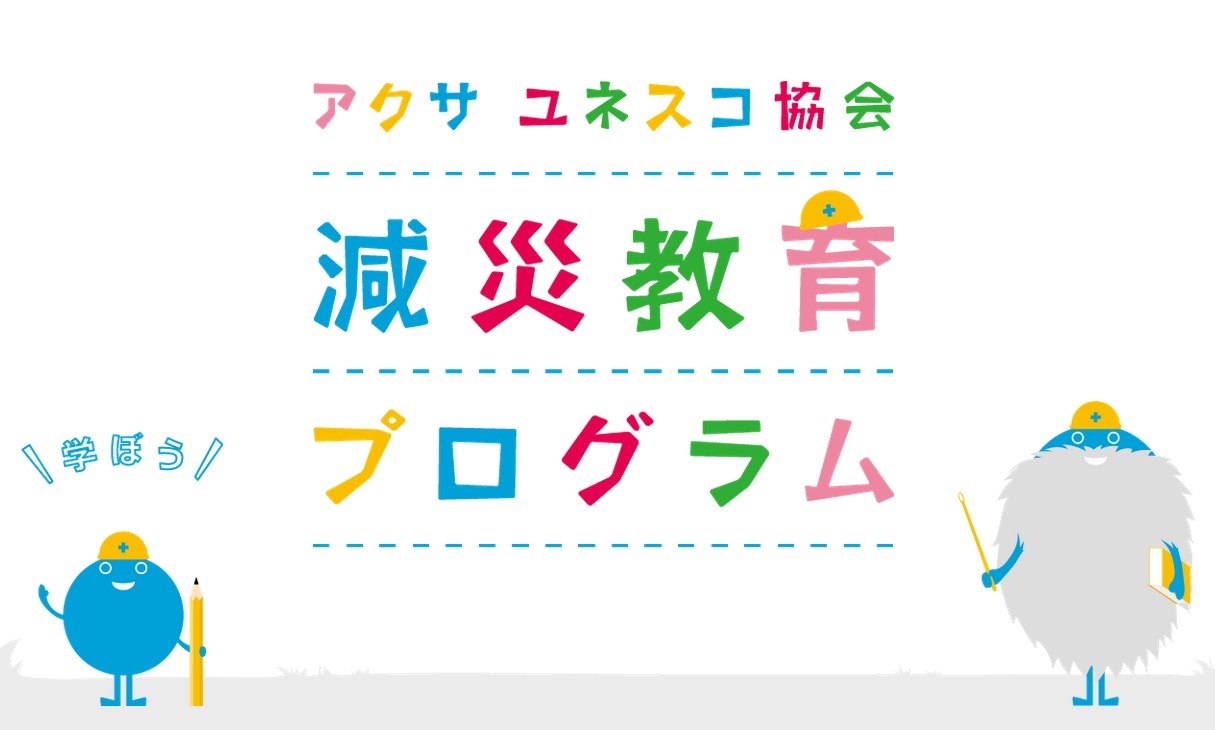
活動において工夫した点
本校では探究活動のカリキュラムが系統的に作られており、フィールドワークも充実していることから、これに授業や課外活動をうまく組み込むことで減災・防災についての関心を高めてもらうことができるのではないかと考えた。
2)のスケジュールにまとめた通り、1学期は地理総合の時間に「地理院地図」や「重ねるハザードマップ」を用いて自分たちが暮らす地域で起こりうる自然災害について学んだり、地球温暖化の影響によって大型台風が上陸し、ハザードマップの想定を上回るような自然災害が起こりうる可能性を学んだりした。他にも大地形の分野で津波の仕組みについて確認し、2011年に発生した原子力発電事故が再び起こる可能性があることなども確認した。
そして、2学期に探究活動のフィールドワークで県内の再生可能エネルギーの研究、普及に取り組む大学や企業を訪れた。1学期に地球温暖化による自然災害の被害拡大の可能性、原子力発電事故のことなどについて学んでいたため、生徒たちは再生可能エネルギーの意義を実感しながら話を聞くことができたのではないかと思う。
ただ、水害や土砂災害と違って内陸部に位置している福島高校では、県内沿岸部の高校生に比べて、津波の危険性やそれにともなう原発事故の影響についてどうしても実感しにくい環境にある。そこで、助成金を活用し、エネルギー問題に関心のある生徒たちに大熊町の中間貯蔵施設を見学するプログラムに参加してもらうことにした。このプログラムには、他県の生徒も多数参加しており、原発をめぐる認識の違いなどについても実感してもらえるよい機会となった。

