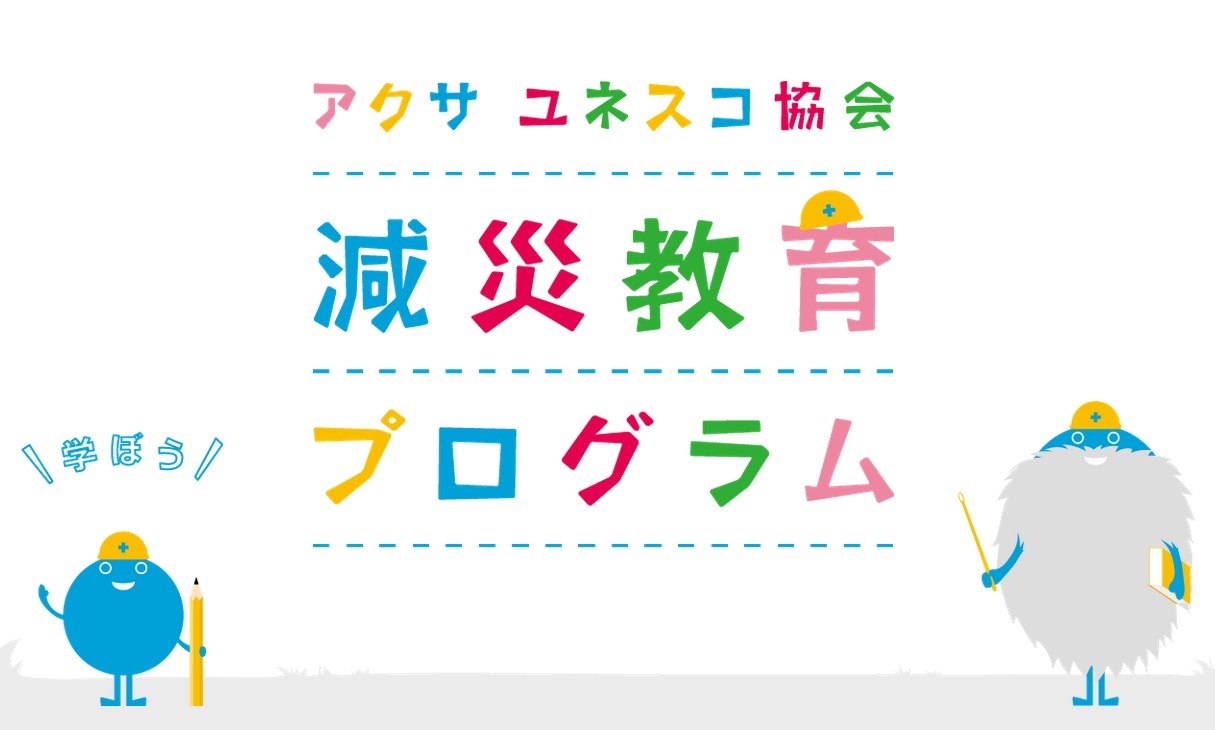
うつぐみの心を守る てーどぅん(竹富)の減災・防災教育
竹富小中学校
活動に参加した児童生徒数/小1~6、中1~3 学年 33 人
活動に携わった教員数/4人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/保護者・地域住民・その他( 気象台・防災士・竹富町役場防災課 ) 37人
実践期間2024年10月12日~2024年10月13日
活動のねらい
親子防災キャンプを行うことで、親子で防災に対する意識を高める。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
〇 実践内容「親子防災キャンプ」
〇 実践の流れ【全児童生徒への事前学習、避難経路作成用のワークシート配布 → 親子防災キャンプ 】
〇 親子防災キャンプスケジュール
日にち
時間
内容
10月12日(土)
10:00
10:30~12:00
13:00~15:30
16:00~
18:00~
21:00~
・地震発生、津波警報発令想定の島内放送
・竹富小中学校屋上へ避難・防災士による講話【体育館】
・体育館にて気象台による講話・実験・クイズ【体育館・体育館周辺】
・防災倉庫の見学と防災体験【備蓄倉庫・体育館周辺】
・夕食準備
・防災食ごはん(防災カレー、アイラップごはん等)【体育館周辺】
・体育館、教室で就寝準備
・就寝
10月13日(日)
7:00~
8:30~
・起床、朝食
・防災キャンプを通してのふりかえり、発表【体育館】
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
〇 研修で学んだことを踏まえた防災キャンプ事前学習を行うことができた。
〇 校内研修で、9月研修会の発表を行った。海洋教育と防災教育でのつながりを共有し、次年度の計画に取り入れてもらった。
〇 本校が島の避難所になっている。助成金を活用することで、避難所になったときに必要な道具を購入できた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
・親子防災キャンプを行うことで、災害(地震・津波)の起こり方について理解し、災害時にどのような対応をすることが適切なのか、保護者も交えて考えさせることができた。
・減災(防災)教育活動の取り組みを島内の各集落に周知することで、防災対策の推奨を行うことができた。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・小学1・2年は、地震・津波の認知が低かったが、親子防災キャンプを行うことで、地震・津波について理解し、どのように対応していくとよいか判断する力が身についた。
・小学3~6年は、地震・津波について理解していたが、防災対策に対しての意識に個人差があった。親子防災キャンプを通して理解を深め、各家庭防災対策を行い、当日も防災バッグをもって避難することができた。
・中学生は、防災対策に対しての意識の個人差や、実際に災害が起きたときにどのような行動をするとよいのか具体的に考えることができなかった。親子防災キャンプのふりかえりの場面において、「災害があったときの家族の集合場所を決めておく」「防災食の準備をする」など、具体的に考えることができるようになった。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・9月の研修会での様子を校内研修で共有したことで、教師にも防災教育の意識を高めることができた。本校は海洋教育に力をいれているため、「海洋×防災」など次年度への教育活動の視野を広げることができた。
・保護者にも参加、協力をしてもらったことで、防災バッグを各家庭準備することができた。
・竹富町役場、気象台、防災士の関係機関と関係をもつことができたため、教育活動で活用していきたい。
4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
・実践から、災害時に、家族でどこに避難をしておくとよいか等の家族会議の重要性を各家庭が感じてくれた。
・保護者を巻き込んでの活動ができた。観光地でもあるため、島をあげての訓練など、地域の方も一緒に活動できるようにしたい。
・次年度以降、継続的に防災教育の取り組みが他教科等と関連づけながら行えるよう、教育計画に位置づける。
〇 実践内容「親子防災キャンプ」
〇 実践の流れ【全児童生徒への事前学習、避難経路作成用のワークシート配布 → 親子防災キャンプ 】
〇 親子防災キャンプスケジュール
| 日にち | 時間 | 内容 |
| 10月12日(土) | 10:00 10:30~12:00 13:00~15:30 16:00~ 18:00~ 21:00~ |
・地震発生、津波警報発令想定の島内放送 ・竹富小中学校屋上へ避難・防災士による講話【体育館】 ・体育館にて気象台による講話・実験・クイズ【体育館・体育館周辺】 ・防災倉庫の見学と防災体験【備蓄倉庫・体育館周辺】 ・夕食準備 ・防災食ごはん(防災カレー、アイラップごはん等)【体育館周辺】 ・体育館、教室で就寝準備 ・就寝 |
| 10月13日(日) | 7:00~ 8:30~ |
・起床、朝食 ・防災キャンプを通してのふりかえり、発表【体育館】 |
〇 研修で学んだことを踏まえた防災キャンプ事前学習を行うことができた。
〇 校内研修で、9月研修会の発表を行った。海洋教育と防災教育でのつながりを共有し、次年度の計画に取り入れてもらった。
〇 本校が島の避難所になっている。助成金を活用することで、避難所になったときに必要な道具を購入できた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
・親子防災キャンプを行うことで、災害(地震・津波)の起こり方について理解し、災害時にどのような対応をすることが適切なのか、保護者も交えて考えさせることができた。
・減災(防災)教育活動の取り組みを島内の各集落に周知することで、防災対策の推奨を行うことができた。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・小学1・2年は、地震・津波の認知が低かったが、親子防災キャンプを行うことで、地震・津波について理解し、どのように対応していくとよいか判断する力が身についた。
・小学3~6年は、地震・津波について理解していたが、防災対策に対しての意識に個人差があった。親子防災キャンプを通して理解を深め、各家庭防災対策を行い、当日も防災バッグをもって避難することができた。
・中学生は、防災対策に対しての意識の個人差や、実際に災害が起きたときにどのような行動をするとよいのか具体的に考えることができなかった。親子防災キャンプのふりかえりの場面において、「災害があったときの家族の集合場所を決めておく」「防災食の準備をする」など、具体的に考えることができるようになった。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・9月の研修会での様子を校内研修で共有したことで、教師にも防災教育の意識を高めることができた。本校は海洋教育に力をいれているため、「海洋×防災」など次年度への教育活動の視野を広げることができた。
・保護者にも参加、協力をしてもらったことで、防災バッグを各家庭準備することができた。
・竹富町役場、気象台、防災士の関係機関と関係をもつことができたため、教育活動で活用していきたい。
4)実践から得られた教訓や課題と、次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
・実践から、災害時に、家族でどこに避難をしておくとよいか等の家族会議の重要性を各家庭が感じてくれた。
・保護者を巻き込んでの活動ができた。観光地でもあるため、島をあげての訓練など、地域の方も一緒に活動できるようにしたい。
・次年度以降、継続的に防災教育の取り組みが他教科等と関連づけながら行えるよう、教育計画に位置づける。
活動内容写真
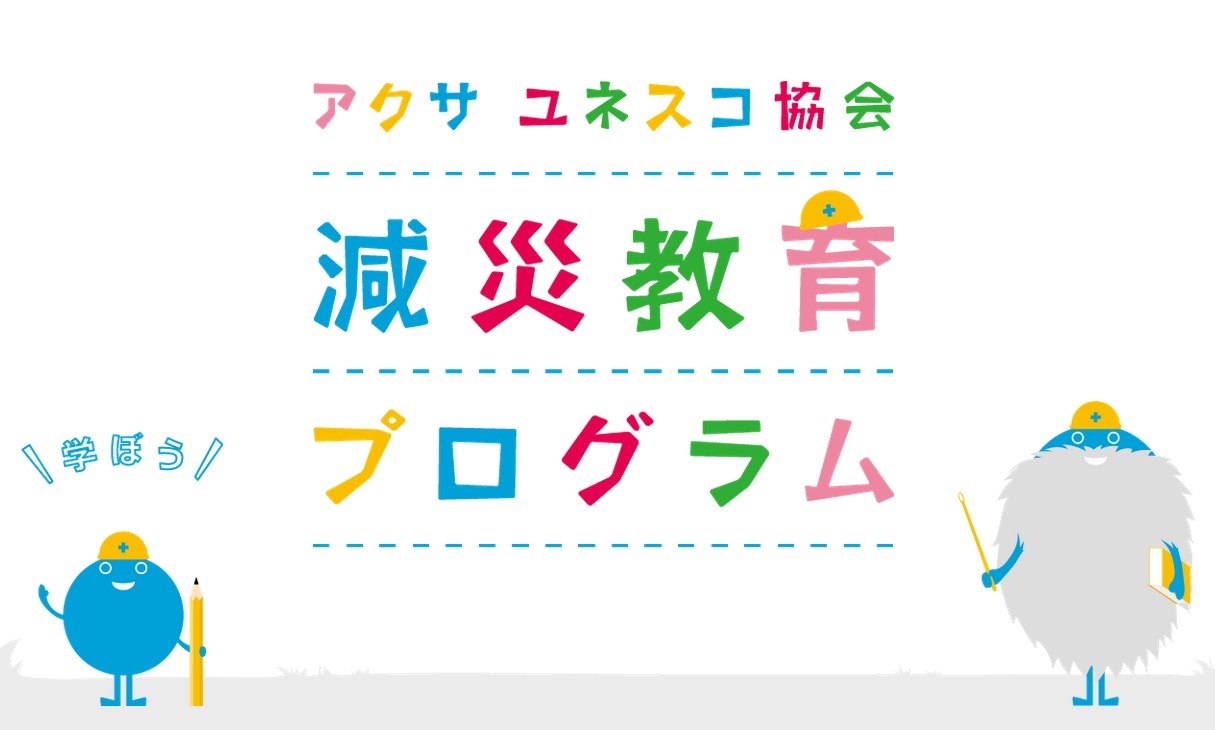
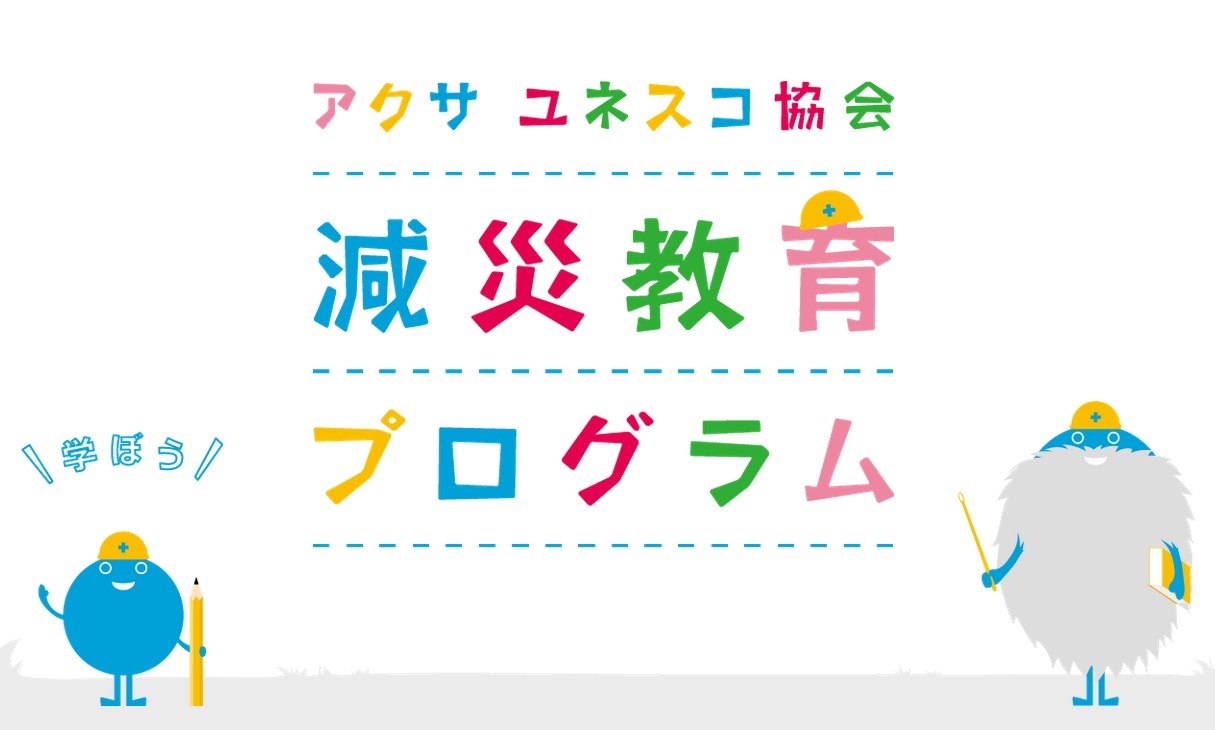
活動において工夫した点
・9月の研修に参加する直前に、地域の子ども会主催「親子防災キャンプ」が行われると決まった。本校職員も子ども会の役員でもあったため、学校共催として親子防災キャンプの取り組みを一緒に行うことができた。

