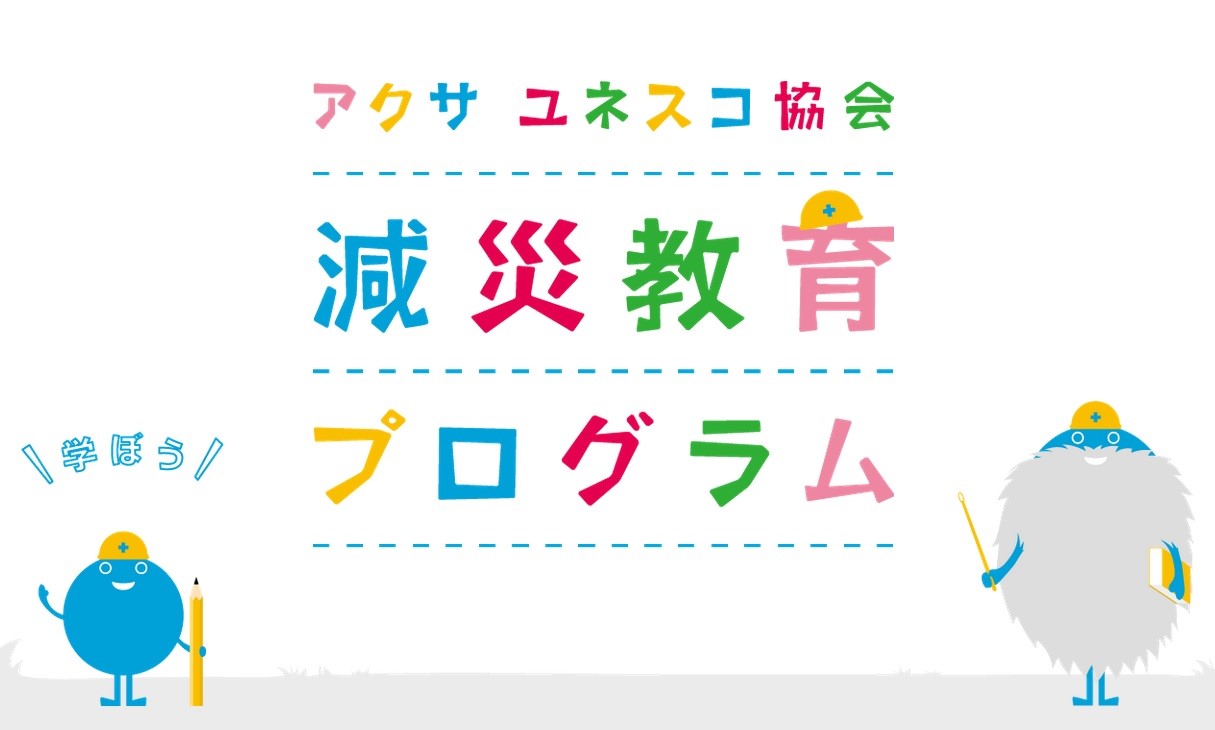
津波による犠牲者ゼロへの提言
高知県立須崎高等学校
活動に参加した児童生徒数/1~3学年273人
活動に携わった教員数/50人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/70人
実践期間2015年4月1日~2016年2月12日
活動のねらい
過去の南海地震においても津波の被害に遭ってきたこの土地で、命を守るべく地域と協力し、避難道の開拓を行い、避難訓練を実施してきた。校舎内には緊急持ち出し袋や備蓄品を設置し、心肺蘇生法や応急手当てを学び実践することで他者の命をも救えるように意識を高めている。近年はそれらを地域住民の方々とともに実践する活動を行ってきた。さらに津波による犠牲者ゼロへの提言を須崎市に提出し、防災・減災への意識改革を図る提言内容を実施する。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
6/18
防災プロジェクトチーム協議会
7/9
中学校への防災出前授業①(南海トラフ地震について、備蓄品・持ち出し品・応急手当)
7/21
防災研修会(ホームセンターフタガミの防災士による家具固定方法の実際について)
7/22
地域(岡本地区)での防災・減災への意識調査実施
8/22
KOCHI防災危機管理展2015にて防災劇上演
8/27,28
地域での家具固定ボランティア実施
9/18
第6回南海地震フォーラム開催(基調講演 矢守克也氏、実践発表 高知大学、須崎高校)
10/16
中学校への防災出前授業②(南海トラフ地震について、備蓄品・持ち出し品・応急手当)
2)9月研修会での学びから自校の実践に活かしたこと、研修会を受けての自校の活動の変更・改善点、
昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点、助成金の活用で可能になったことなど。
被災地の視察、防災教育を熱心に行っている階上中学校への訪問等で自分たちのすすめる防災・減災活動をさらに進化(深化)させたいと思い、自分たちの掲げる意識改革、特に高齢者への対策では、助成金で家具固定用品を購入し、ボランティアに入ることができ、少しずつではあるが意識改革につながる活動ができている。いつもは予算もない中での活動であり、今回は自分たちがやりたいと思うことが実現できたことが大きかった。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
平成21年度より取り組んでいる減災(防災)教育活動は東日本大震災後に大きく転換を図り、「命を守る」という視点に重きを置いて校内外で取り組んできた。現在は「命を守り育てる」活動を地域のみならず、高知県下に広げていこうとしている。活動を継続してやってきた中で、減災(防災)の提言書を作成し、須崎市にも提出した。防災・減災パートナー協定を締結している須崎市は主にハード面、本校は主にソフト面で減災(防災)への意識改革に、できることから着手している。すでに防災CMの作成・放映を実現したが、今回地域に入り、住民と対話し、啓発を行いつつ、家具固定とのボランティアを行った。人との信頼関係を築き、ともに課題解決に向けて動き出そうとする姿勢を創りだすという活動が本校生徒のみならず、地域住民へも、「だれもが地域の防災リーダーになり、減災(防災)につなげ、未来をのこす」という意識向上につながっている。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
本年度は、高齢者の意識改革をめざし、“あきらめない、逃げるお年寄り”をつくるために、地域調査の実施、地域の方々との協議、ボランティアに入るための実技講習などを行った。生徒たちは地域調査を実施するにあたっての準備を地域の方の意見を参考にしながら、スムーズに地域に入れるように企画・実施していった。地域の住民との交流も問題なく、グループによっては、急きょ老人ホームへの訪問を試み、生徒たちは臆せず向き合い、和やかに調査を終えることができた。その後、認知症を患う高齢者の避難方法など新たな課題も見つけてきたと報告があった。課題を明らかにし、新たな対策を立案するまでになった生徒たちを見て、防災リーダーとなりつつあることを実感している。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
本年度の取り組みにも地域の方々から協力をいただき、企画・立案後の協議、実施に至るまで共に汗を流していただいた。本来は地域が主となって実施しなければいけないことを、本校が先導してやってくれるのでぜひ協力をしたいとの言葉をもらい、生徒たちの活動にも力がはいっている。さらに、この地域での調査及び家具固定ボランティアの活動に同感して、須崎市地震・防災課がこの取り組みを須崎市内全域に連携して実施していきたいとの申し出があり、今後協議を行い、活動を広げていく予定である。
4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望
本年度取り組んだ、高齢者の意識を変える家具固定ボランティアの活動は、まだ始まったばかりで須崎市内さらには高知県内にまで家具固定率があがるような活動を継続したい。本校独自の取り組みでは、限界のあることも多く、他校と連携して進めていく体制を検討している。(県内の高校生による防災サミットの開催や各市町村の防災活動の運営に高校生が加わり、防災・減災に対する新たな企画、実践する)
| 6/18 | 防災プロジェクトチーム協議会 |
| 7/9 | 中学校への防災出前授業①(南海トラフ地震について、備蓄品・持ち出し品・応急手当) |
| 7/21 | 防災研修会(ホームセンターフタガミの防災士による家具固定方法の実際について) |
| 7/22 | 地域(岡本地区)での防災・減災への意識調査実施 |
| 8/22 | KOCHI防災危機管理展2015にて防災劇上演 |
| 8/27,28 | 地域での家具固定ボランティア実施 |
| 9/18 | 第6回南海地震フォーラム開催(基調講演 矢守克也氏、実践発表 高知大学、須崎高校) |
| 10/16 | 中学校への防災出前授業②(南海トラフ地震について、備蓄品・持ち出し品・応急手当) |
昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点、助成金の活用で可能になったことなど。
被災地の視察、防災教育を熱心に行っている階上中学校への訪問等で自分たちのすすめる防災・減災活動をさらに進化(深化)させたいと思い、自分たちの掲げる意識改革、特に高齢者への対策では、助成金で家具固定用品を購入し、ボランティアに入ることができ、少しずつではあるが意識改革につながる活動ができている。いつもは予算もない中での活動であり、今回は自分たちがやりたいと思うことが実現できたことが大きかった。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
平成21年度より取り組んでいる減災(防災)教育活動は東日本大震災後に大きく転換を図り、「命を守る」という視点に重きを置いて校内外で取り組んできた。現在は「命を守り育てる」活動を地域のみならず、高知県下に広げていこうとしている。活動を継続してやってきた中で、減災(防災)の提言書を作成し、須崎市にも提出した。防災・減災パートナー協定を締結している須崎市は主にハード面、本校は主にソフト面で減災(防災)への意識改革に、できることから着手している。すでに防災CMの作成・放映を実現したが、今回地域に入り、住民と対話し、啓発を行いつつ、家具固定とのボランティアを行った。人との信頼関係を築き、ともに課題解決に向けて動き出そうとする姿勢を創りだすという活動が本校生徒のみならず、地域住民へも、「だれもが地域の防災リーダーになり、減災(防災)につなげ、未来をのこす」という意識向上につながっている。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
本年度は、高齢者の意識改革をめざし、“あきらめない、逃げるお年寄り”をつくるために、地域調査の実施、地域の方々との協議、ボランティアに入るための実技講習などを行った。生徒たちは地域調査を実施するにあたっての準備を地域の方の意見を参考にしながら、スムーズに地域に入れるように企画・実施していった。地域の住民との交流も問題なく、グループによっては、急きょ老人ホームへの訪問を試み、生徒たちは臆せず向き合い、和やかに調査を終えることができた。その後、認知症を患う高齢者の避難方法など新たな課題も見つけてきたと報告があった。課題を明らかにし、新たな対策を立案するまでになった生徒たちを見て、防災リーダーとなりつつあることを実感している。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
本年度の取り組みにも地域の方々から協力をいただき、企画・立案後の協議、実施に至るまで共に汗を流していただいた。本来は地域が主となって実施しなければいけないことを、本校が先導してやってくれるのでぜひ協力をしたいとの言葉をもらい、生徒たちの活動にも力がはいっている。さらに、この地域での調査及び家具固定ボランティアの活動に同感して、須崎市地震・防災課がこの取り組みを須崎市内全域に連携して実施していきたいとの申し出があり、今後協議を行い、活動を広げていく予定である。
4)実践から得られた教訓や課題と今後の改善に向けた方策や展望
本年度取り組んだ、高齢者の意識を変える家具固定ボランティアの活動は、まだ始まったばかりで須崎市内さらには高知県内にまで家具固定率があがるような活動を継続したい。本校独自の取り組みでは、限界のあることも多く、他校と連携して進めていく体制を検討している。(県内の高校生による防災サミットの開催や各市町村の防災活動の運営に高校生が加わり、防災・減災に対する新たな企画、実践する)
活動内容写真
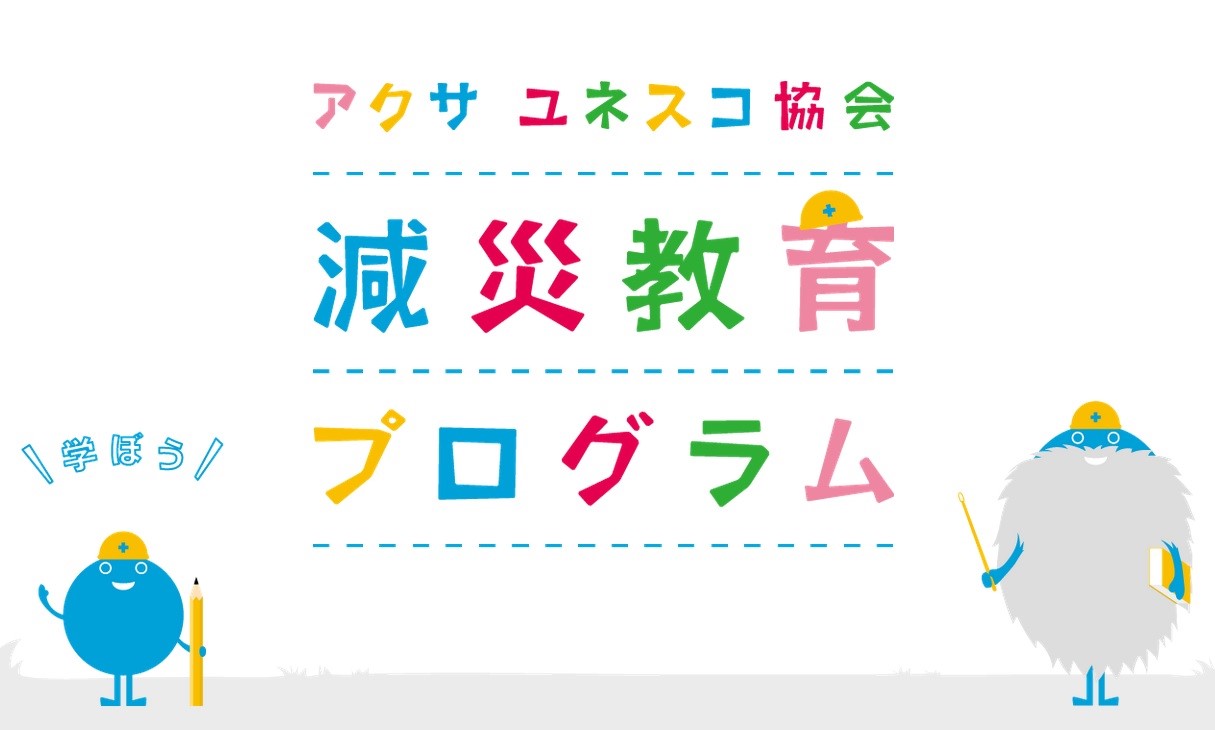
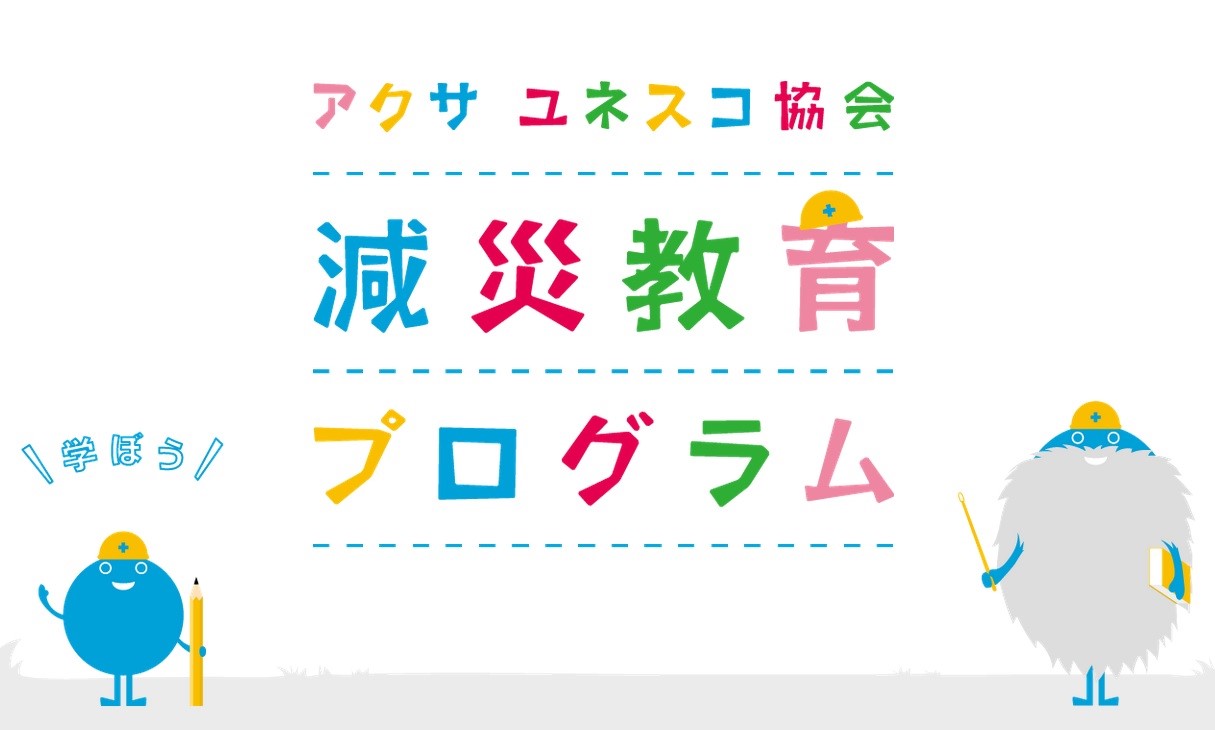
活動において工夫した点
地域の方々と連携して新たな防災・減災活動を企画し、実施していくにはどのような手順が必要なのかということを念頭に置いて、綿密な打ち合わせを行い活動した。地域調査で個々の家庭に入っていく時も、事前にお知らせの文書を岡本地区長経由で地域に回してもらった。自主防災組織会長は、各家庭を回ってくれて活動の趣旨について説明をし、高校生が地域に入りやすいようにしてくれた。
本校の防災活動の中心は防災プロジェクトチームであり、その活動は全校へ伝達し浸透させていくように努めている。全体への指導においても、生徒一人ひとりが地域の防災リーダーになれるような防災LH(3年間の系統的な指導計画にもとづいておこなっているが、防災行動力育成を重視した内容を実施)、救急法講習会は、1年生は保健の授業で、2年生は救命入門コース、3年生で普通救命講習と段階を追って実施している。救急法講習会の講師は、応急手当普及員及び応急手当指導員の資格を持った本校の教員が講師を務める(現在校内に14名)生徒と教員が一体となって防災教育活動をすすめるという体制を継続して行っている。

