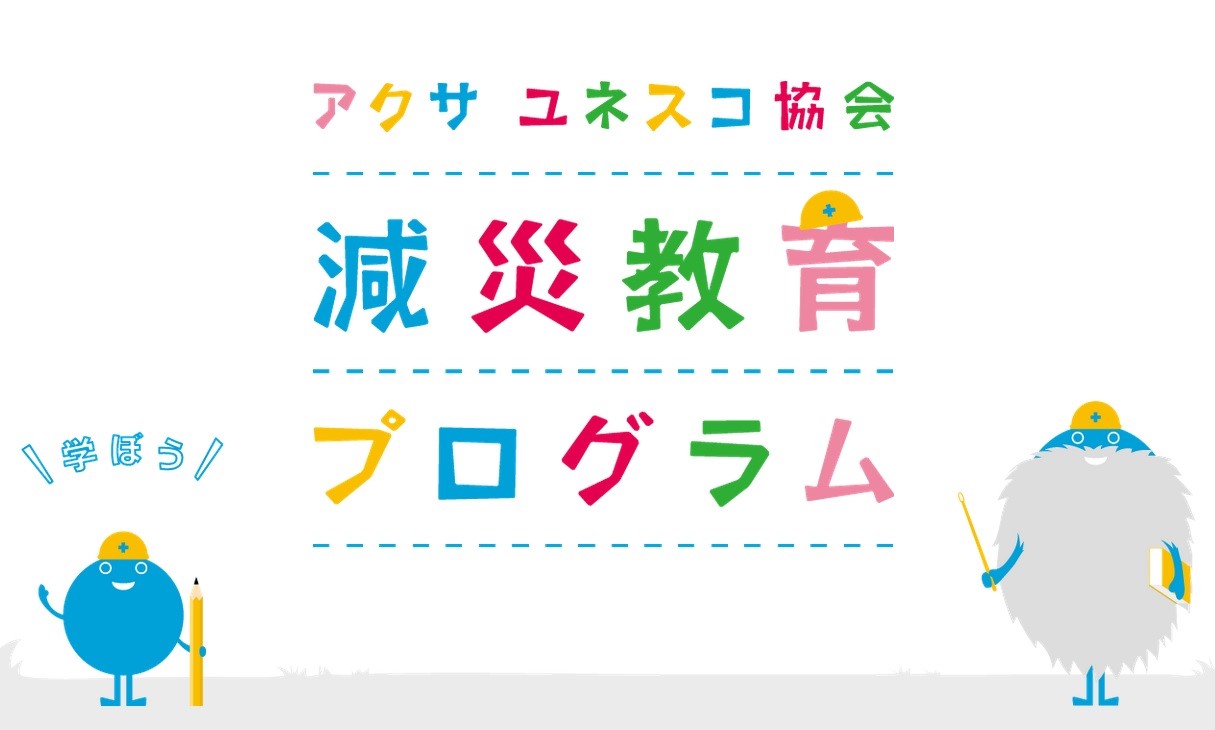
生徒が主体的に課題解決に向けて探究し、地域の一員として提案、実践する防災・減災教育
新潟市立小針中学校
活動に参加した児童生徒数/1~3学年821人
活動に携わった教員数/56人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/14人
実践期間2021年4月7日~2022年3月12日
活動のねらい
防災・減災についての認識を深めて自分事とし、自ら課題を設定してその解決に向けた探究活動を進め、地域社会に貢献する実践力を育む。さらに、防災・減災の学習や防災士を中心とした地域の方々と連携した活動を通して、自助・共助・公助の視点からバリアフリー、グローバル化への対応、性的マイノリティなど現代社会が抱える課題に目を向け、積極的に関わり解決していこうとする生徒を育てる。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
1年
校区内防災
フィールドワーク
防災体験
学習
家族防災
会議
体験のまとめ
合同避難訓練の参加
探究学習の基本を学ぶ
2年生の防災学習の発表会への参加、振り返り
2年
校区外フィールドワーク
(新潟探訪)
防災現地調査学習
事前事後学習
修学旅行事前事後防災学習※いわき市・双葉町・浪江町
合同避難訓練の参加
修学旅行事防災学習のまとめと発表
3年
防災現地調査学習
事前事後学習
さすけなぶる探究活動、
まとめ
課題解決の探究活動、合同避難訓練の準備、企画運営、
発表会
学習の振り返り、卒業に向けて
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。
昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
<変更・改善点>
・カリキュラムの作成と見直しに着手し、当校でも学習指導で重視する7つの能力・態度を総合的な学習での各学年の防災に関わる学習活動に位置づける検討を開始した。
・防災学習シートを参考に、各学習活動の学習シートを作成・修正してファイリングをした。また、防災学習シートを全職員が閲覧できよう準備を進めているところである。
・各学年で防災・減災に関する体験活動を行い、その学びをまとめて発表する形に偏りがちだったものを、生徒の問いを生かして課題を設定し、自ら探究していくプロセスを学習活動の中に入れていく計画づくりに着手できるようになった。
<助成金>
・生徒主体(3年生による防災運営委員会)で企画運営した合同避難訓練で、防災運営委員の生徒たちは、避難経路の各所に立哨して購入した小型のハンドマイクで指示伝達し、スムーズな避難になるよう有効活用した。さらに、防災運営委員の生徒が互いに避難訓練時の誘導や委員どうしで連絡を取り合うためのトランシーバーの台数が整い、今後、より円滑な生徒主体の活動が可能になった。
・感染症予防のための消毒用アルコールを補充し、実際に合同避難訓練で実際を想定して使用した。
・各学年の防災学習の際のファシリテーション、学習のまとめや発表用に購入した模造紙を惜しみなく使用した。また、生徒数が多い中学校のため学習活動では多くの模造紙を必要とし、全校生徒の防災学習や活動のまとめ、発表のための模造紙の補充ができた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
当校では、総合的な学習の柱をキャリアから防災に変更して4年目(令和3年度現在)になった。防災を核にし、3年間を通した学習を終え、防災カリキュラムの見直しと取組の再検討に着手するスタートを切った。その際、9月の研修会で紹介された作成の経緯、身につけたい能力や態度、地域に貢献できる姿のイメージを参考にして再検討をすすめ、令和4年度から運用する予定である。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
及川先生の講義であったESDで構築する自助・共助・公助の視点を活動の目的やねらいに加えて修正した。そして、3年生の防災に関わる最後の課題解決学習のまとめの際にその3つの視点を伝え、防災に関わるバリアフリー、グローバル化への対応、性的マイノリティなど現代社会が抱える課題まで踏み込む生徒が複数いたことは、成果があった。N助の視点の導入についても今後検討する予定である。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・教師側では、特に各学年の総合担当の職員と研修後に総合部会を開き、生徒が身につけたい7つの能力・態度を活動の中で位置づけるような修正を共通理解し、運用する準備を行った。
・地域の自治会や防災士、行政の総務課など関係機関のスタッフに、防災学習のどの場面でどんな支援を必要とするか見直した。コロナ禍のため、合同避難訓練では防災士を10名以下に限定して参加してもらい、防災運営委員の生徒の指示や避難する生徒の観察と評価を専門的な視点で当日と事後にアドバイスして頂いた。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
・9月の研修会に向けて頂いた防災学習シートの冊子のような自校オリジナルの学習シートを作成して蓄積する。
・今後も持続可能な防災学習のカリキュラムに修正・運用していく。
・ESDやSDGsの視点を防災教育や総合的な学習全体に関連させて実践し、各教科との横断化を図る。
・生徒に身につけさせたい能力や態度、姿を学習活動の中で明確にし、生徒の変容を見取って評価する体制づくり。
・生徒が主体的に課題解決できる、指導と働きかけ、教材の開発や校内研修体制の整備を行う。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1年 | 校区内防災 フィールドワーク |
防災体験 学習 |
家族防災 会議 |
体験のまとめ | 合同避難訓練の参加 探究学習の基本を学ぶ |
2年生の防災学習の発表会への参加、振り返り | ||||||
| 2年 | 校区外フィールドワーク (新潟探訪) |
防災現地調査学習 事前事後学習 |
修学旅行事前事後防災学習※いわき市・双葉町・浪江町 合同避難訓練の参加 |
修学旅行事防災学習のまとめと発表 | ||||||||
| 3年 | 防災現地調査学習 事前事後学習 |
さすけなぶる探究活動、 まとめ |
課題解決の探究活動、合同避難訓練の準備、企画運営、 発表会 |
学習の振り返り、卒業に向けて | ||||||||
<変更・改善点>
・カリキュラムの作成と見直しに着手し、当校でも学習指導で重視する7つの能力・態度を総合的な学習での各学年の防災に関わる学習活動に位置づける検討を開始した。
・防災学習シートを参考に、各学習活動の学習シートを作成・修正してファイリングをした。また、防災学習シートを全職員が閲覧できよう準備を進めているところである。
・各学年で防災・減災に関する体験活動を行い、その学びをまとめて発表する形に偏りがちだったものを、生徒の問いを生かして課題を設定し、自ら探究していくプロセスを学習活動の中に入れていく計画づくりに着手できるようになった。
<助成金>
・生徒主体(3年生による防災運営委員会)で企画運営した合同避難訓練で、防災運営委員の生徒たちは、避難経路の各所に立哨して購入した小型のハンドマイクで指示伝達し、スムーズな避難になるよう有効活用した。さらに、防災運営委員の生徒が互いに避難訓練時の誘導や委員どうしで連絡を取り合うためのトランシーバーの台数が整い、今後、より円滑な生徒主体の活動が可能になった。
・感染症予防のための消毒用アルコールを補充し、実際に合同避難訓練で実際を想定して使用した。
・各学年の防災学習の際のファシリテーション、学習のまとめや発表用に購入した模造紙を惜しみなく使用した。また、生徒数が多い中学校のため学習活動では多くの模造紙を必要とし、全校生徒の防災学習や活動のまとめ、発表のための模造紙の補充ができた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
当校では、総合的な学習の柱をキャリアから防災に変更して4年目(令和3年度現在)になった。防災を核にし、3年間を通した学習を終え、防災カリキュラムの見直しと取組の再検討に着手するスタートを切った。その際、9月の研修会で紹介された作成の経緯、身につけたい能力や態度、地域に貢献できる姿のイメージを参考にして再検討をすすめ、令和4年度から運用する予定である。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
及川先生の講義であったESDで構築する自助・共助・公助の視点を活動の目的やねらいに加えて修正した。そして、3年生の防災に関わる最後の課題解決学習のまとめの際にその3つの視点を伝え、防災に関わるバリアフリー、グローバル化への対応、性的マイノリティなど現代社会が抱える課題まで踏み込む生徒が複数いたことは、成果があった。N助の視点の導入についても今後検討する予定である。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・教師側では、特に各学年の総合担当の職員と研修後に総合部会を開き、生徒が身につけたい7つの能力・態度を活動の中で位置づけるような修正を共通理解し、運用する準備を行った。
・地域の自治会や防災士、行政の総務課など関係機関のスタッフに、防災学習のどの場面でどんな支援を必要とするか見直した。コロナ禍のため、合同避難訓練では防災士を10名以下に限定して参加してもらい、防災運営委員の生徒の指示や避難する生徒の観察と評価を専門的な視点で当日と事後にアドバイスして頂いた。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望 ・9月の研修会に向けて頂いた防災学習シートの冊子のような自校オリジナルの学習シートを作成して蓄積する。
・今後も持続可能な防災学習のカリキュラムに修正・運用していく。
・ESDやSDGsの視点を防災教育や総合的な学習全体に関連させて実践し、各教科との横断化を図る。
・生徒に身につけさせたい能力や態度、姿を学習活動の中で明確にし、生徒の変容を見取って評価する体制づくり。
・生徒が主体的に課題解決できる、指導と働きかけ、教材の開発や校内研修体制の整備を行う。
活動内容写真
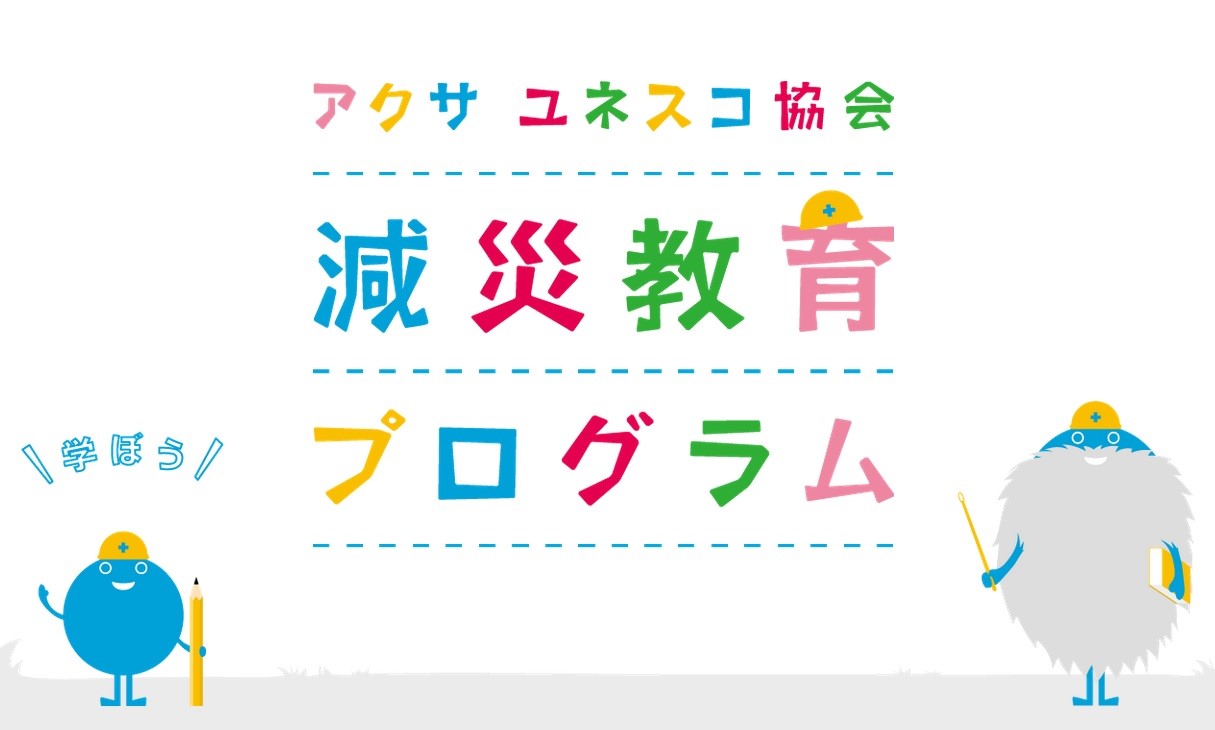
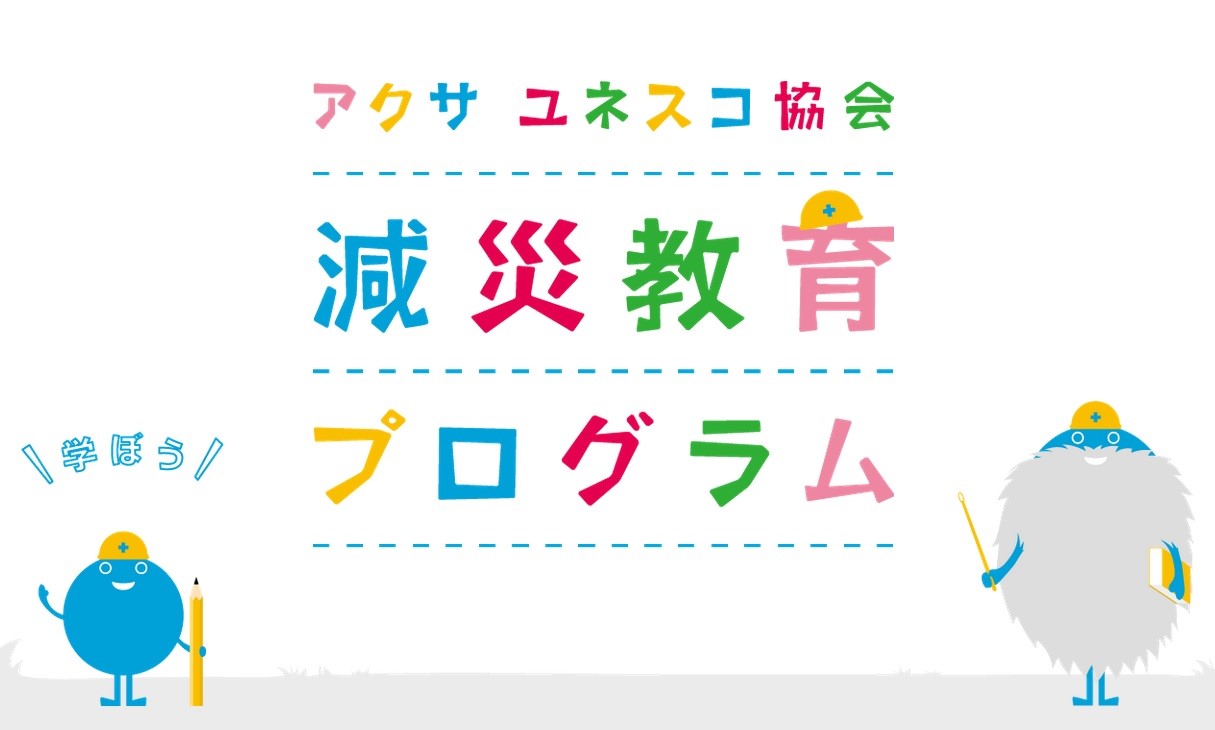
活動において工夫した点
・防災学習のまとめでは、学習用ダブレット端末と紙ベースとを併用して、映像やデータ、文字や絵など工夫してわかりやすく発表する生徒が多かった。学びのある発表やアウトプットの手段をさらに研修していきたい。
・3年生の発表会では、コロナ禍のため発表場所を分散させた上、全校生徒と学習に関わった地域の防災士も参加し、学びの共有をした。

