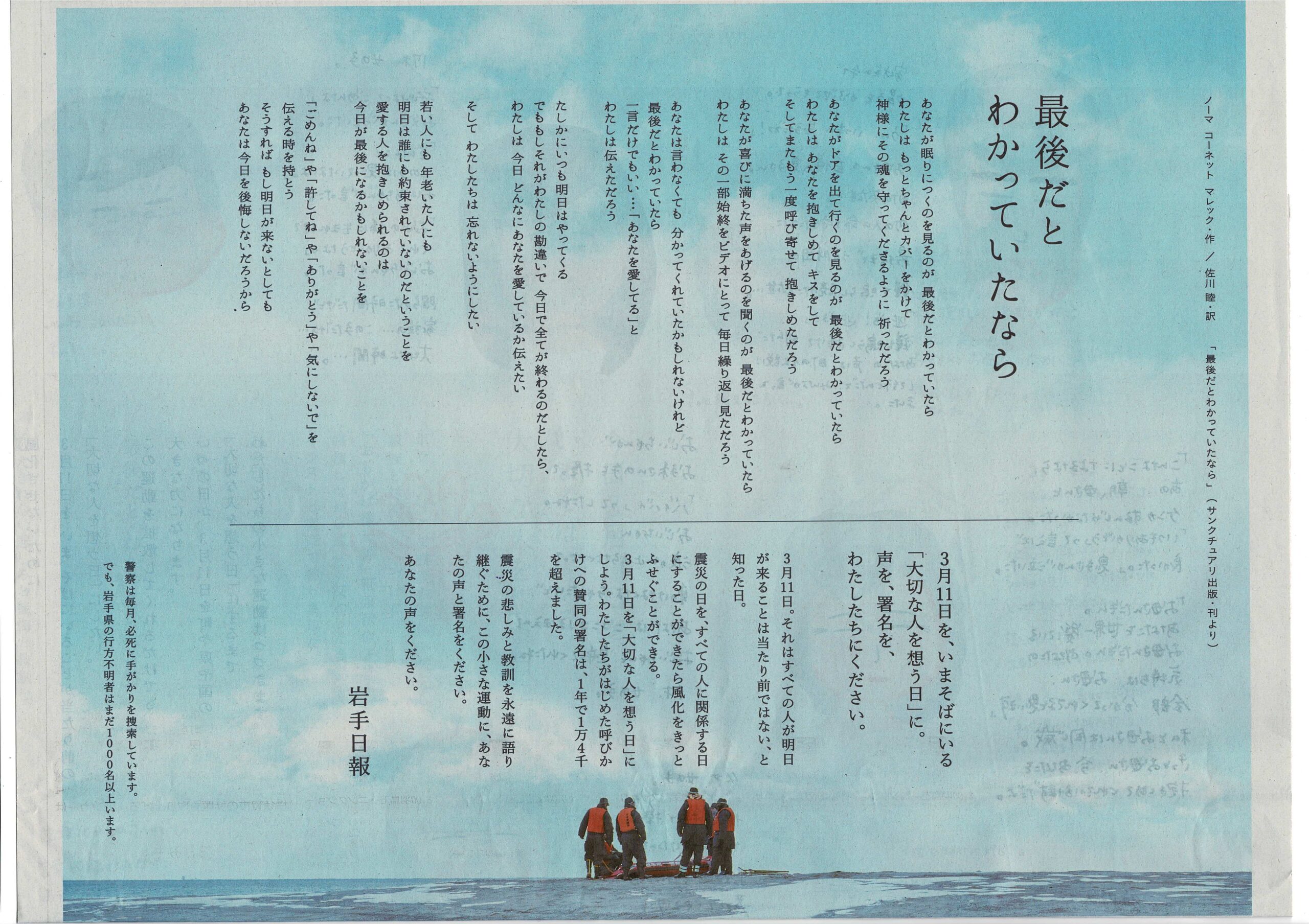
郷土を愛し、郷土を支える人材の育成
わが町陸前高田の誇りと未来~「つなぐプロジェクト」を通して~
陸前高田市立高田第一中学校
活動に参加した児童生徒数/1~3学年272人
活動に携わった教員数/30人
活動に参加した地域住民・保護者等の人数/100人
実践期間2018年4月6日~2018年12月25日
活動のねらい
本校は、市の少子高齢化、東日本大震災による人口減少等により、第一中学校と気仙中学校が平成30年4月に統合した新設校である。震災により市は壊滅的状況となり、海沿いにあった気仙中の校舎は全壊し、閉校となった山間の校舎を利用し7年間の学校生活を送ってきた。第一中学校は、校舎や体育館の大きな損傷はなかったが、校庭に仮設住宅が作られ、震災からまもなく8年になろうとする平成31年1月現在も校庭は復旧整備途中であり、教育活動には使用できない状況である。
このような厳しい環境にありながらも、教職員と生徒は、様々な支援や限られた教育環境でも行事等を実施できることに感謝しつつ、当たり前の学校生活を送ることに全力で取り組んできた。また、これまでの教育活動では、生徒の心のケアを最優先し、震災で受けた苦しみや悲しみを思い出させないようにするため、「減災や防災」という部分を最小限としつつ、地域への感謝、人とのかかわりの大切さ等にその重点を置いてきた。
一方、震災の風化が懸念され始めていることも事実である。現在の中学3年生は大震災発生直後の小学2年生であり、大震災の記憶は薄い。また、教職員、中学生全体としても「減災・防災」のための知識・技能をはじめ、緊急時の対応訓練等も十分に経験しているとは言えない。
そこで、本校では、「学校は、生徒と教職員の命を預かるところ、生徒に生き抜く力を教育するところ」の理念のもと、これまでの復興教育※1を強化し、「減災・防災」に重点をおいた「つなぐプロジェクト」として取り組むこととした。この「つなぐプロジェクト」は、過去と現在、未来をつなぐこと、あるいは、中学生と地域をつなぐこと等、様々な関係をつなぎたいという意図を込めて設定したプロジェクト名であり、総合的な学習の時間を軸として教育活動全体に位置づけている。このプロジェクトにより、生徒自らの命を守る主体的な行動、進んで他の人々や地域のために活動できる力の育成、災害のメカニズムや防災の情報を活用する力等を育成し、わが町陸前高田が復興へ向かうために、中学生としての学びを深め元気を発信したいと考えている。
そのため、具体的には、新設校としての「つなぐプロジェクト」の活動記録を整理するため及び次年度以降の「減災・防災」教育の手引きとして使用するための「防災学習ノート(まもるくんノート)」を作成し、活用することで、防災学習のための基盤づくりと同時にこれまで十分ではなかった「減災・防災」教育への取り組みを強化していきたいと考えている。
※1復興教育:岩手県では、大震災を辛く悲しい経験というとらえだけにするのではなく、そこから得た教訓を県全体で共有し、活かしていこうとしている。その教育を「いわての復興教育」と名付け、全県の公立学校がそれぞれの地域の児童生徒や地理的状況等に応じて展開している。この復興教育のねらいは「郷土を愛し、その復興・発展を支える人材を育成するために各学校の教育活動を通して、3つの教育的価値【いきる:生命や心についての学び】【かかわる:人や地域についての学び】【そなえる:防災や安全についての学び】を育てること」である。
活動内容
1)実践内容・実践の流れ・スケジュール
※資料参照
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。
昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
①昨年度までは生徒の心のケアを重視し、「復興教育」の3つの教育的価値のうち、【いきる】【かかわる】を中心とした実践であった。今年度は、自助・共助を中心とした【そなえる】を充実させ、3年間を貫く防災学習の在り方を模索し始めた。
②まちづくりや減災・防災について、地域を巻き込んだ活動を目指し、地域連携や発信を活動に位置づけた。
③助成金により平成29、30年度の活動を中心とした「防災学習ノート」を作成し、今までの活動を整理し見直すことができた。
④「防災学習ノート」の作成をとおして、次年度以降の防災学習の全体計画を見直す機会となり、職員が防災教育についてより強く意識して取り組み、教科指導においても防災をテーマとした教材開発や学習活動を取り入れるなどの工夫が見られた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
・今までの活動や記録を整理し、活動を見直すとともに、防災教育【そなえる】の重要性を再認識できたこと。
・学年ごとに実践していた復興教育を改め、学校全体で3年間を貫く継続した防災学習の計画を立て、実践したこと。
・実践をしながらプログラムの修正をする等、防災の視点で生徒にとってよりよい活動となるよう話し合うことができたこと。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・1年生:「HUG」の実施による「守られる立場から守る立場」への意識の変化。「つなぐポスター」の制作及び地域への配布により、地域と関わることの楽しさや大切さを実感し、地域の一員としての自覚が高まった。
・2年生:「防災マップを歩こう」の活動を通して、自分たちの地域の安全や避難経路について主体的に考えるようになった。実際に歩くことにより、安全な場所まで避難するには通路整備が不十分である等の検証をし、生徒自身で協働して改善案を考え、市当局に問題提起をすることができた。学校での学びを日常生活に活かした場面であった。
・3年生:防災体験学習を通して、災害弱者という立場など地域全体の防災について考えるようになった。いざという時に中学生としてどんなことができるか具体的なイメージを持つことができた。
・生徒会活動:防災に関する生徒集会を企画し、全校生徒が楽しみながら考え、話し合い、活動することにより防災意識が高まった。(防災クイズ・地域への防災フライヤー等)
・市防災マイスター養成講座に参加する生徒が見られるなど、防災意識の高まりや主体的行動が見られるようになった。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・職員HUG研修等を通して、防災教育への関心と「生徒の命を守る」という意識を高め、指導の在り方を考えることができた。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
①明確なねらいのもと体験的な活動を仕組むことで、生徒は防災について主体的に学び、考え、実践への意欲を持つようになる。これは、本校がこれまで避けてきた防災学習を今年度取り入れたことによるものととらえている。
②学校の学びで得たことを生徒が家庭や日常生活の中で活かす減災・防災につなげるための働きかけの工夫が必要である。
③減災・防災教育を、より充実させるために教職員全体でのカリキュラム・マネジメントを進めていきたい。
④東日本大震災から8年が過ぎようとしており、生徒だけではなく教職員においても震災の風化が感じられる部分がある。また人事異動により実践が途絶えることも懸念される。そこで、今回の助成金で作成した防災学習ノート「まもるくんノート」を活用することにより、次年度以降も教職員で共通理解を図りながら、よりよい活動を推進していきたい。
※資料参照
2)9月研修会の学びの中から自校の実践に活かしたこと。研修会を受けての自校の活動の変更・改善点。
昨年度まで(助成金を受ける前)の実践と今年度の実践で変わった点。助成金の活用で可能になったこと。
①昨年度までは生徒の心のケアを重視し、「復興教育」の3つの教育的価値のうち、【いきる】【かかわる】を中心とした実践であった。今年度は、自助・共助を中心とした【そなえる】を充実させ、3年間を貫く防災学習の在り方を模索し始めた。
②まちづくりや減災・防災について、地域を巻き込んだ活動を目指し、地域連携や発信を活動に位置づけた。
③助成金により平成29、30年度の活動を中心とした「防災学習ノート」を作成し、今までの活動を整理し見直すことができた。
④「防災学習ノート」の作成をとおして、次年度以降の防災学習の全体計画を見直す機会となり、職員が防災教育についてより強く意識して取り組み、教科指導においても防災をテーマとした教材開発や学習活動を取り入れるなどの工夫が見られた。
3)実践の成果
①減災(防災)教育活動・プログラムの改善の視点から
・今までの活動や記録を整理し、活動を見直すとともに、防災教育【そなえる】の重要性を再認識できたこと。
・学年ごとに実践していた復興教育を改め、学校全体で3年間を貫く継続した防災学習の計画を立て、実践したこと。
・実践をしながらプログラムの修正をする等、防災の視点で生徒にとってよりよい活動となるよう話し合うことができたこと。
②児童生徒にとって具体的にどのような学び(変容)があり、どのような力(資質・能力・態度)を身につけたか。
・1年生:「HUG」の実施による「守られる立場から守る立場」への意識の変化。「つなぐポスター」の制作及び地域への配布により、地域と関わることの楽しさや大切さを実感し、地域の一員としての自覚が高まった。
・2年生:「防災マップを歩こう」の活動を通して、自分たちの地域の安全や避難経路について主体的に考えるようになった。実際に歩くことにより、安全な場所まで避難するには通路整備が不十分である等の検証をし、生徒自身で協働して改善案を考え、市当局に問題提起をすることができた。学校での学びを日常生活に活かした場面であった。
・3年生:防災体験学習を通して、災害弱者という立場など地域全体の防災について考えるようになった。いざという時に中学生としてどんなことができるか具体的なイメージを持つことができた。
・生徒会活動:防災に関する生徒集会を企画し、全校生徒が楽しみながら考え、話し合い、活動することにより防災意識が高まった。(防災クイズ・地域への防災フライヤー等)
・市防災マイスター養成講座に参加する生徒が見られるなど、防災意識の高まりや主体的行動が見られるようになった。
③教師や保護者、地域、関係機関等(児童生徒以外)の視点から
・職員HUG研修等を通して、防災教育への関心と「生徒の命を守る」という意識を高め、指導の在り方を考えることができた。
4)実践から得られた教訓や課題と次年度以降の実践の改善に向けた方策や展望
①明確なねらいのもと体験的な活動を仕組むことで、生徒は防災について主体的に学び、考え、実践への意欲を持つようになる。これは、本校がこれまで避けてきた防災学習を今年度取り入れたことによるものととらえている。
②学校の学びで得たことを生徒が家庭や日常生活の中で活かす減災・防災につなげるための働きかけの工夫が必要である。
③減災・防災教育を、より充実させるために教職員全体でのカリキュラム・マネジメントを進めていきたい。
④東日本大震災から8年が過ぎようとしており、生徒だけではなく教職員においても震災の風化が感じられる部分がある。また人事異動により実践が途絶えることも懸念される。そこで、今回の助成金で作成した防災学習ノート「まもるくんノート」を活用することにより、次年度以降も教職員で共通理解を図りながら、よりよい活動を推進していきたい。
活動内容写真
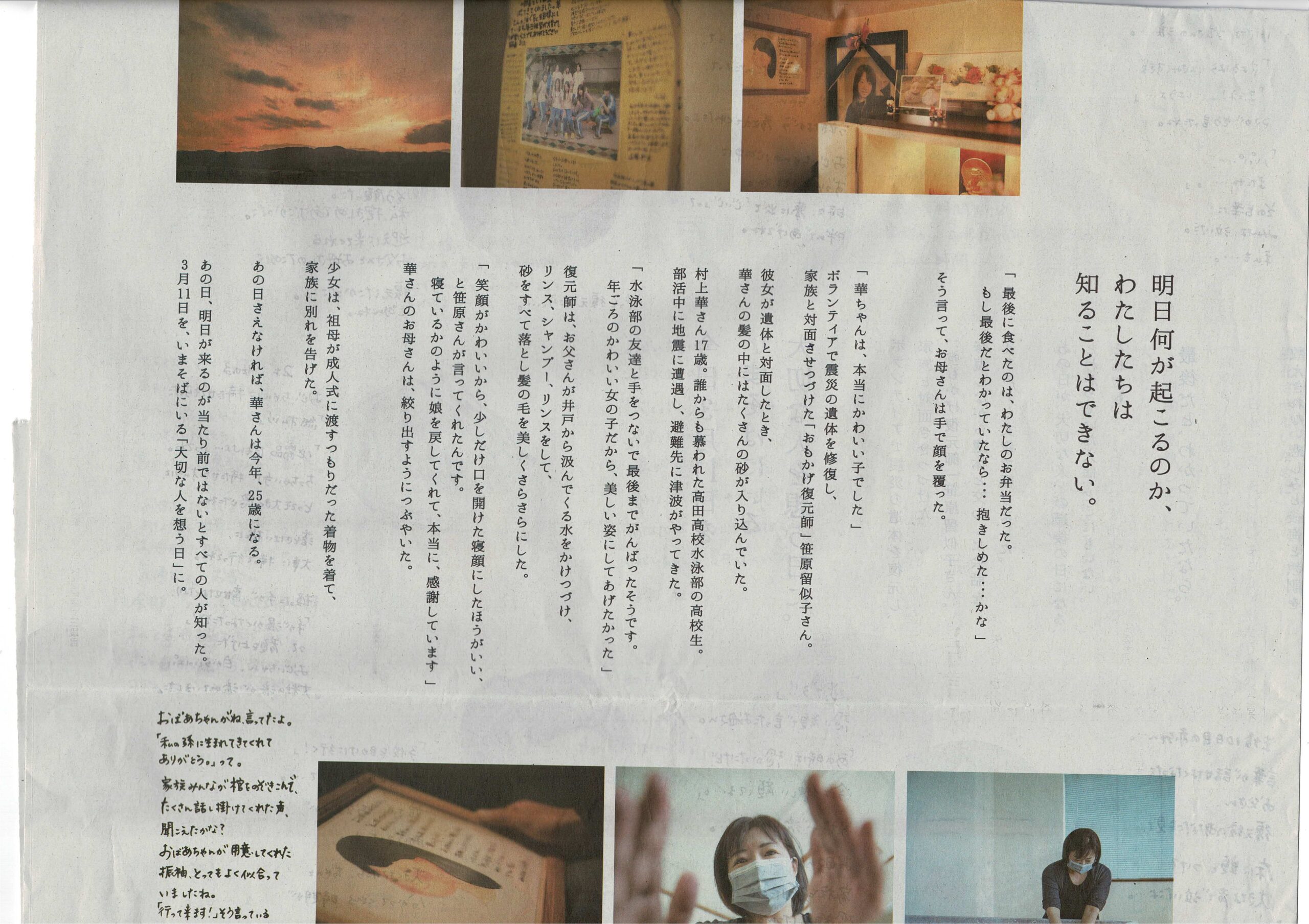
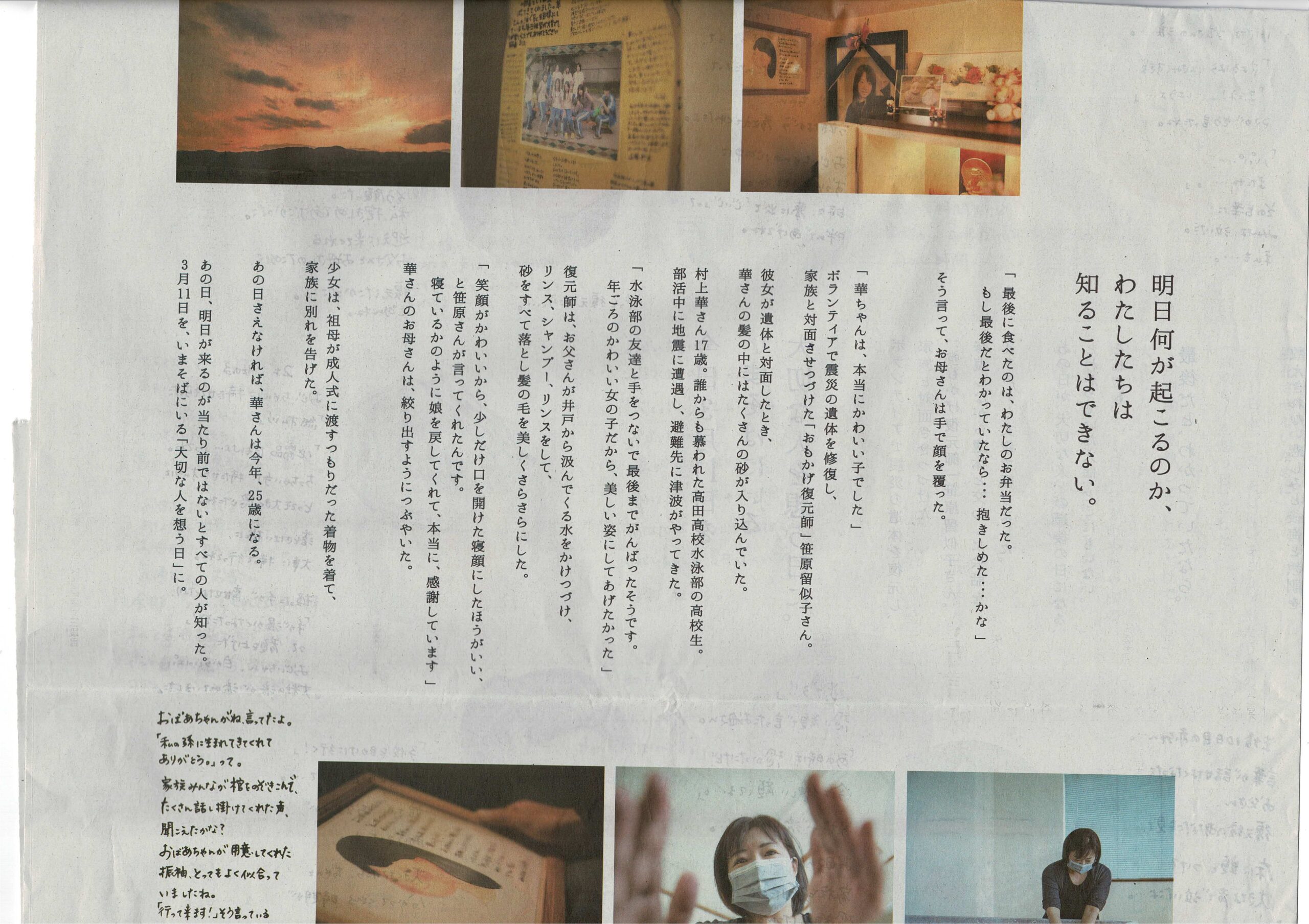
活動において工夫した点
①本市は多数の死者・行方不明者が出た地域であることから、生徒の多くが人的・物的被害の影響を心に抱えて生活している。そのため、3年生の避難所運営の活動を防災体験学習に変更するなど、生徒の心のケアに配慮しながら活動を進めたこと。
②震災を直接的に知らない生徒・教職員が増える中、震災後の本校の教育活動等の貴重な記録を残しながら、3年間を貫く防災
教育のあり方について検討した。それを受け「防災学習ノート」を作成し、次年度以降の活動につなげようとしている。

